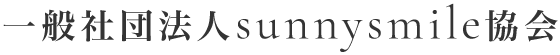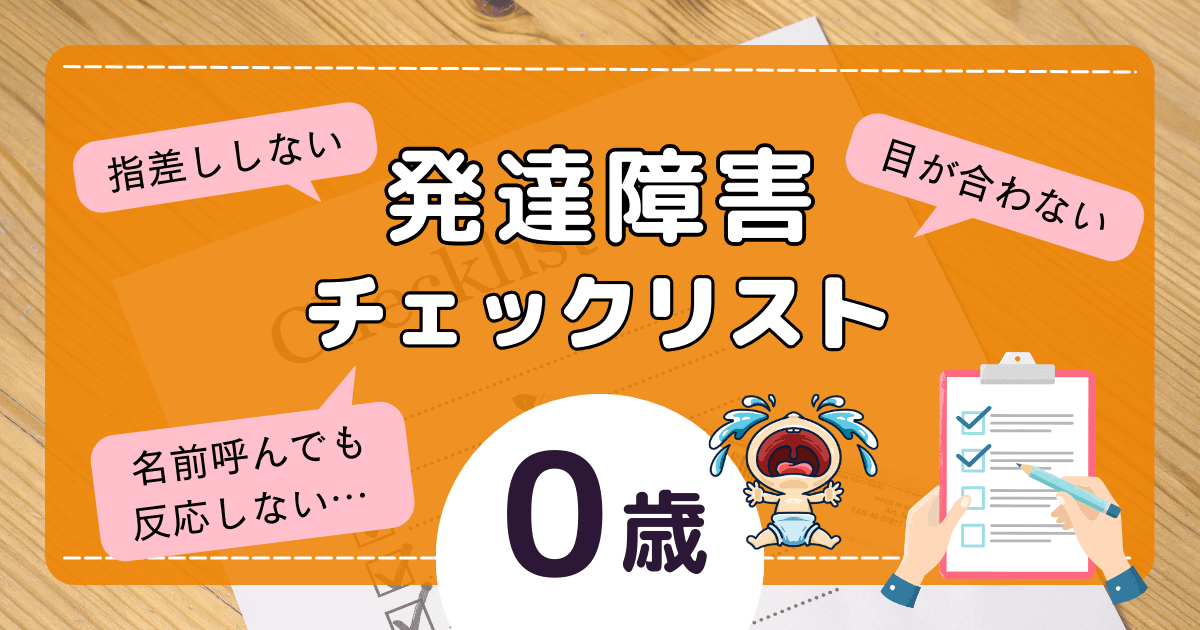私は発達障害の長女(5歳)と、定型発達の次女(1歳)を育てるママです。
長女に発達障害の特徴がはっきりと出始めたのは3歳の頃でしたが、今になって思い返すと、実は0歳の頃から違和感を感じる場面がいくつもありました。
なかなか寝てくれない、目が合わない、指差しをしない…
私の長女、普通の子どもと比べてなんだかちょっと違うかも?
ただ当時の私は「初めての育児だから私の気にしすぎかも」と思い込み、特に対策をすることもなく、ただ様子を見るだけで月日が過ぎていきました。
でも、長女が3歳のときに“子育てコーチング”という学びに出会い、0歳からの関わり方や赤ちゃんの発達に必要なことを初めて知ったとき、「ああ、もっと早く知っていれば…」と心から後悔しました。
あの頃の私に「赤ちゃんの違和感が気になるのであれば、これは知っておいてほしい!」と伝えたくなるような情報をまとめました。
同じように「うちの子、発達が遅いかも?」「何だか他の子どもと違う気がする」と悩んでいるママ、参考にしていただけると嬉しいです!
こちらもオススメ → 【体験談】子育ての悩み誰に相談する?無料で解決しない理由と私の選択
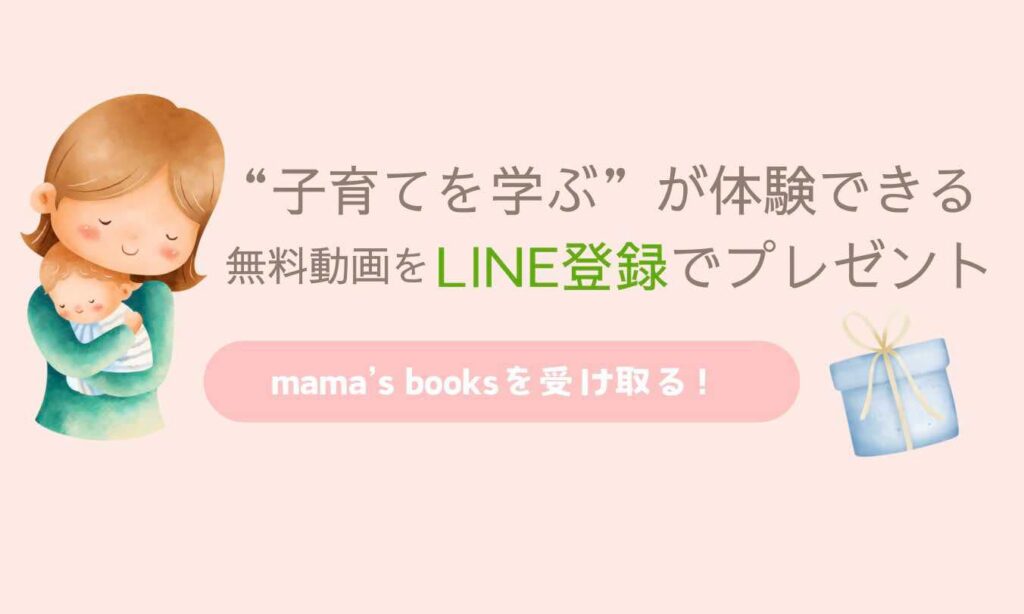
目次
0歳の発達障害の特徴・チェックリスト

まず知っておいていただきたいのは、0歳の時点で「発達障害です」と診断されることはほとんどないということです。
しかし、実際に診断がついたお子さんの0歳の頃の様子を振り返ると、「当時こんな特徴があったな…」という共通点がいくつか見えてきます。
私の長女の体験や発達支援に関わる資料などをもとに、チェックリストを作成しました。
| □ 視線が合わない |
| □ 感情表現が乏しい(泣かない・あやしても笑わないなど) |
| □ 抱っこを嫌がる |
| □ 音や光に敏感な様子が見られる(大きな音で激しく泣くなど) |
| □ 名前を呼んでも無反応 |
| □ 夜なかなか寝てくれない、寝てもすぐ起きる |
| □ 指差ししない |
| □ クレーン現象が見られる(ママの手を取って自分の欲しいものを指し示す行為) |
チェックリストに多く当てはまったことで、もしかして自分の子どもが発達障害なのでは?と思われたママ、特徴が多く当てはまった=発達障害だと決まるわけではありません。
2005年に施行された発達障碍者支援法によると、発達障害の定義は「脳の機能障害」と記載されており、一般的にも「先天性の脳の障害だから、ママの子育てのせいではない。治せない」というような認知がされていると思います。
なお、0歳の発達にはとても大きな個人差があり、少し遅れていても、大きくなればできるようになるということがほとんどです。
実際に、私の長女も名前を呼んでも無反応の赤ちゃんでしたが、2歳になって名前を呼ぶと、声のする方へ振り返ったり「はーい」と返事をしてくれるようになりました。
目に見えていなくても、少しずつ確実に発達は進んでいますので、今はできないことであっても「まだその発達段階にきていない」と思って見守ることも大切だと思います。
【経験談】2人育てて感じた育児の後悔…0歳児の違和感を気のせいと思った結果

長女に発達障害の診断がついたとき、「私の育て方のせいじゃない」と頭では分かっていました。
ただ、どうしても「もっと早く気づいてあげられたら…」「小さい時にできることがあったんじゃないか」と悔やむ気持ちは消えませんでした。
そんな中で出会ったのが“子育てコーチング”で、子どもの発達に合わせた関わり方や、ママの声かけの大切さを学ぶ中で、長女の育児で私に足りなかったことにも気づかされました。
実際に経験した私の後悔と実際に子育てコーチングを取り入れた子どもたちの成長についてご紹介します。
3歳で発達障害と分かるまで…0歳の違和感は気のせいだと思い何もせず
発達障害と診断された現在5歳の長女ですが、今思えば、赤ちゃんの頃から発達の特徴が見られていました。
- 夜は11時まで寝ず、朝6時には起きて昼寝もしない
- あやしても笑わない(たまに笑っても、表情はわずかにしか変化しない)
- 指差しをしない
- 名前を呼んでも反応がない
先ほどご紹介したチェックリスト項目の中で、いくつかが当てはまっていました。
ただ、発達障害の子によく見られる「クレーン現象(大人の手を使って欲しい物を指し示す行動)」がなかったため、「大丈夫かな」「気のせいかも」と思い、結局そのまま様子を見ることにしました。
「個人差があるし、もう少し見てみよう」と思い続けたのですが、2歳半を過ぎても言葉がほとんど出ず、2語文もたまにしか言えない状態…
相変わらず名前を呼んでもほとんど反応がなく、ようやく「これは何かあるのかもしれない」と発達相談に踏み出したのが、長女が3歳の時で診断は発達障害でした。
0歳の時に感じていた違和感が発達障害であったことを知った時、原因が分かってほっとしたのと同時に、もっと早く気づいて行動すればよかったと後悔したのを今でも覚えています。
0歳から子育てコーチングを取り入れた次女は10ヶ月で発語!
そんな私が子育てコーチングを学び始めたのは、長女の発達障害が分かった時のことで、長女は3歳(年少)、次女はまだ0歳でした。
癖やこだわりの強い長女との関わり方に悩んでいたことをきっかけに学び始めたのですが、子どもとの関わり方を見直す中で、「ママの声かけは0歳からちゃんと伝わっている」「声かけは脳の発達に影響する」ということを知りました。
すでに3歳になっていた長女でしたが、今からでも取り返せると意気込んで学んだことを実践した結果、少しずつ長女のこだわりや思いを理解できるようになり、少なかった言葉数も徐々に増やしていくことができました。
そして、当時生後3ヶ月だった次女にも、学んだことをすぐに取り入れてみることにしました。
語りかける、目を見て話す、スキンシップを増やす、五感を使った遊びを意識するなど、学んだことを日々続けていたところ…
なんと、生後10ヶ月で発語が始まり、1歳3ヶ月で2語文、1歳8ヶ月では3語文が言えるように!
2歳前に「ママ、今日お外いったね」「トマトと卵焼き、おいしいね」「わーい、やったー」とものすごい勢いで喋り続けている姿は、まるで“言葉の天才”で子育てコーチングを学んでよかったと心から思いました。
でも同時に、「もし長女のときに、もっと早くこういう関わりをしていたら、スムーズに言葉が出ていたのかもしれないな…」と、やっぱり後悔の気持ちも湧いてきました。
私の0歳育児で不足していたのは「会話」と「経験」
0歳の時期は、五感(見る・聞く・触れる・嗅ぐ・味わう)がぐんぐん発達する大切な時期で、この時期にたくさんの「体験」をすることが、発達にも大きく影響すると言われています。
それを知って私が長女の育児で不足していたなと感じているのは、「会話」と「経験」の2つです。
長女が生後3ヶ月のとき、ちょうどコロナ禍になり、外出もほとんどせず、家の中で静かに過ごす日々が続いていました。
人と会う機会も少なく、私自身も初めての育児に不安を抱えていた時期で、今思えば、長女に対して声かけも少なかったと思います。
もちろん、それが言葉の遅れの直接の原因かどうかは分かりませんが、赤ちゃん時代にどんな刺激を受けて育つか、どんな言葉をどれだけ浴びたかという「環境」が、子どもの成長に与える影響はとても大きいと今は感じています。
実際に声かけや五感を意識して育てた次女が、2歳前に会話のキャッチボールができたり、お友だちの名前やキャラクター名をハキハキ言っている様子を見て、0歳から会話をすること、色々な経験をさせることの影響の大きさを実感しています。
五感遊びについてはこちらの記事でも詳しく紹介しております。
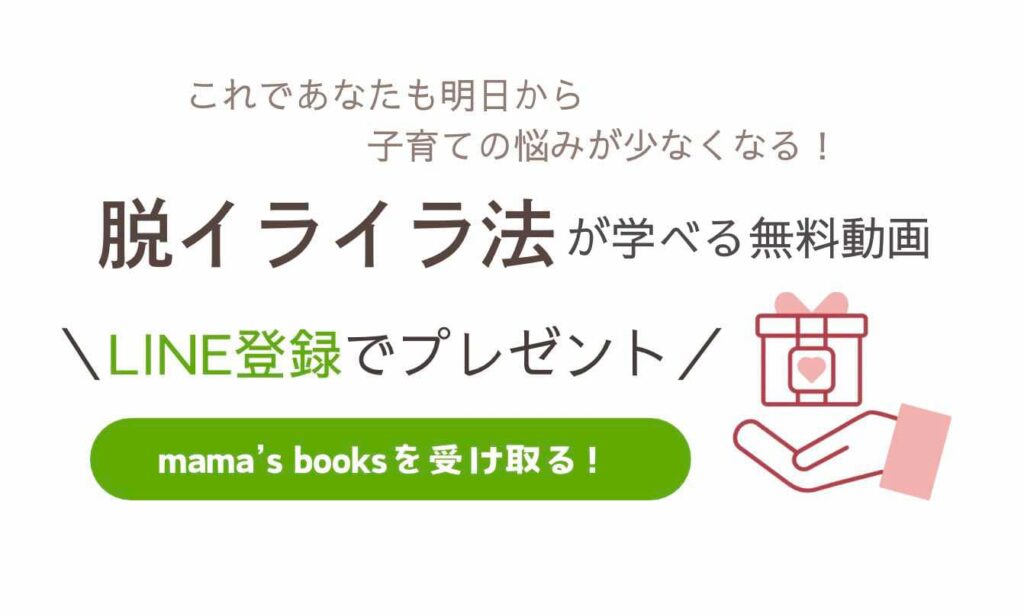
発達基準が気になる方必見!基準から外れた姉妹を育てたママからのアドバイス
初めての子どもを育てるママは発達の目安から外れていることで不安を感じることが多いと思います。
そんなママに安心していただけるように、私の娘2人の発達経過について暴露しちゃいます!
| 発達の目安 | 長女の場合 | 次女の場合 | |
| 首すわりはいつ頃? | 3~4ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 寝返りはいつ頃? | 5~6ヶ月 | 5ヶ月 | 7ヶ月 |
| おすわりはいつ頃? | 7~8ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
| ハイハイはいつ頃? | 8~10ヶ月 | 8ヶ月 | 10ヶ月 |
| つかまり立ちはいつ頃? | 9ヶ月~ 10ヶ月 | 9ヶ月 | 1歳2ヶ月 |
| 一人で立ったのはいつ頃? | 1歳頃 | 1歳 | 1歳4ヶ月 |
| 一人で上手に歩けたのはいつ? | 1歳3ヶ月~ 1歳5ヶ月 | 1歳1ヶ月 | 1歳6ヶ月 |
| 「ママ」「パパ」など意味のある言葉を話したのはいつ? | 1歳2ヶ月~ 1歳6ヶ月 | 2歳6ヶ月 | 10ヶ月 |
| 2語文を話したのはいつ? | 2歳頃 | 2歳8ヶ月 | 1歳2ヶ月 |
| 名前を呼んだら振り向くようになった | 6ヶ月~ 9ヶ月 | 2歳以降 | 6ヶ月 |
| 指差し(共感の指差し)が見られるようになった | 9ヶ月頃 | ? | 9ヶ月 |
| 笑いかけると笑い返すようになった | 2~3ヶ月 | ? | 3ヶ月頃 |
| 音や話し声のする方に顔を向けようとする | 2~3ヶ月 | ? | 1歳以降 |
長女の欄にある「?」は赤ちゃんの時から見られなかったもので、実際に発達障害の特徴にも当てはまる項目でもあります。
そして、ご覧になって分かると思いますが、2人とも見事に発達の目安から外れた経験をしています。
運動は得意ですが発語が遅い長女と、歩くより先におしゃべりを習得した次女…
赤ちゃん時代は発達の基準通りとはいかない道を歩んできた2人ですが、自分のペースで成長しており、今では5歳となった長女はある程度の会話はできるようになり、ダンスが大好きな優しい女の子に成長しました。
一方でもうすぐ2歳になる次女は、1人で立ったり歩き始めが遅い傾向がありましたが、今は小走りの練習を笑いながら楽しんでおり、毎日歌やおしゃべりを披露しております。
0歳の頃は「この子、大丈夫かな…」と心配することもありましたが、振り返ってみると、心配していたことの多くは、時が経つにつれて自然とできるようになっていたことの方が多かったです。
すべての子どもが同じように成長するわけではありませんし、みんなそれぞれのペースでちゃんと前に進んでいるんだなと、今は実感しています。
そして発達の目安から少し外れているように見えても、できないことばかりに目を向けず、今その子ができることに目を向けてあげることが何より大切です。
もし発達障害の子どもであったとしても、ゆっくりですがいつかできるようになる日がきますので、心配しすぎず、ゆっくり見守ってあげてくださいね。
0歳育児で後悔しないで!おうちで発達を促す方法と親の心構え
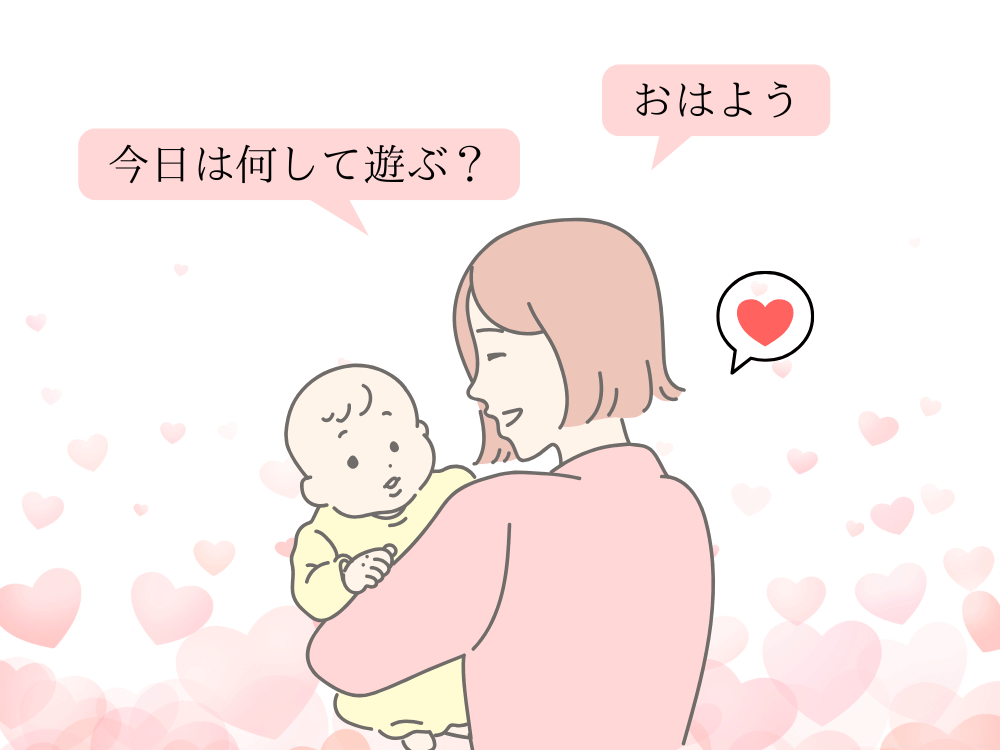
発達の遅れ、発達障害のチェックリストに当てはまるものが多い…
0歳の子どもの発達には個人差があると言われていますし、成長を見守るしかないと思われますが、「今できることがあるならやってみたい」と思うのがママ心ですよね。
赤ちゃんの発達に寄り添った関わり方を、ママが知っておくだけでも、子どもとの関係はぐっと変わっていきます。
私の後悔と反省を踏まえて、0歳からできるおうちで発達を促す方法と親の心構えについてご紹介します。
反応がなくとも毎日話しかける
私は子育てコーチングを学んでから、日常の中でも積極的に子どもに話しかけるように意識するようになりました。
たとえばスーパーでの買い物中も、ただ買い物するのではなく、「このトマト美味しそうだね」「今日は何を作ろうか?」など、積極的に声をかけていました。
0歳の次女と2人きりのときも同じで、まるで独り言のオンパレードでしたが、それでもいい、むしろ、それがいいんです。
継続して声かけを行った結果でしょうか、次女は2歳前で意思を言葉で正確に伝えるようになりました。
反応がなくても、「届いていないかも」と思っても、赤ちゃんはちゃんとママの声を聞いています。
歌や絵本の読み聞かせも同じで、赤ちゃんが楽しそうに反応するなら、それをとことん繰り返してあげるといいですよ。
スキンシップを積極的にとる
発達障害があると、これからの生活の中で「うまくできない」経験が増え、自己肯定感が下がりやすくなると言われています。
だからこそ、赤ちゃんのうちから「あなたはそのままで大丈夫」と感じられるような愛情の土台が大切となってきます。
その土台のひとつが、スキンシップです。
とはいえ、発達障害の特性によっては、触られるのが苦手な子もいます。
特に手や頭など、過敏な部位を嫌がることもあるので、無理に抱っこしたりする必要はありません。
手をそっと握るだけでもいいし、優しく声をかけるだけでも十分です。
「ママはいつもあなたの味方だよ」という想いは、スキンシップを通して、赤ちゃんにもきっと伝わっていきます。

違和感は否定せず「個性」として受け止める
「目が合いにくい」「音への反応が鈍い」といった違和感を感じると、ママは心配になって、「どうにかしなきゃ!」と焦ってしまうこともあると思います。
私もかつて同じ思いがあり、なんとか普通に育てなきゃと、目を合わせようと必死になったり、できないことばかりに目がいってしまったり…
ただ私の長女は私の気持ちを察していたのか、私の気持ちが不安定になると機嫌が悪くなったり急に泣き出すことが多くありました。
子どもの“特徴”をママがマイナスに受け止めてしまうと、それは言葉にしなくても、子どもに伝わってしまいます。
そしてそれは将来、「私はできない子」「ダメな子」と、自信を失ってしまう可能性もあります。
だからこそ、まずは「この子にはこの子のペースがあるんだ」と、個性として受け止めてあげることが大切です。
それは、発達を見守る上でとても心強い土台になりますし、自己肯定感を上げてこれから先の困難を乗り越える力を養うことができます。
他の子どもと比較しすぎない
育児をしていると、どうしても目に入ってくるのが、同じ月齢や年齢の子どもの成長ぶりです。
「○ヶ月で寝返りしたって」「もうつかまり立ちしてるの?」
そんな情報を耳にすると、自然と自分の子どもと比べてしまい、「うちの子、大丈夫かな…」と不安になることってありますよね。
私も長女の育児中、保育園のお友だちが上手におしゃべりするのを見て、1人だけ全然喋らない我が子と比較してしまい、何度も落ち込んだことがありました。
しかし私の長女が5歳まで成長した今思うのは、子どもの発達は本当に一人ひとり違うということです。
スタートがゆっくりな子もいれば、ある日突然ぐんと成長する子もいます。
比べるとしたら“お友だちやSNSの子ども”ではなく“昨日のわが子”です。
「昨日より5分長く目を合わせてくれた」「前よりも表情が豊かになった」過去の我が子に比べてできるようになったことや小さな変化こそ、見逃さずに喜んであげるのが、今の自分にできることではないかと思います。
他の子と比べて不安になる時間があったら、今日できたこと、頑張っている我が子に目を向けてあげてください。
そして、何よりも頑張って向き合っている自分自身のことも、しっかり褒めてあげてください!
子どもの発達が遅くて心配…sunnysmile協会のママ達に聞いてみよう!

子どもの発達が心配で先の不安が拭えない…もし同じような経験をしたママがいたら不安を払拭できるかも。でもそんな人中々いないし、どうしたら?
そんな不安を抱えているママにおすすめなのがsunnysmile協会の子育て相談です。
相談できる相手は私と同じように子育てコーチングを学んで、実践したことでより良い育児ができているママや、似たような悩みを経験をしてそれを乗り越えたママばかり!
さらに相談はオンラインなので、小さい子どもを連れて外出する必要がなく、自宅にいながら相談することが可能です!
まずは気軽に相談してみてくださいね。
 一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。まとめ
0歳の発達障害チェックリストと違和感を感じた時にママができることについてご紹介しました。
- 発達障害は0歳で診断されることは少ないが、特徴は0歳から現れることもある
- 発達には個人差があり、「目安通りでない=問題」とは限らない
- 声かけ・スキンシップ・五感の刺激など、家庭でもできる関わり方がある
- どんな子も、自分のペースで成長しているので、焦らず見守る気持ちが大切です
0歳の育児はママにできることをやりつつ、個人差を尊重して見守る姿勢も大切です。
「気になるかも」と思った今が動き出すチャンスですので、参考になったと思いましたら、ぜひ今日から取り入れてみてください。
こちらも読まれています→ 【事例】育てにくい赤ちゃんの成長記録10選!性格or発達障害か…特徴を理解して不安解消!
#発達障害 #チェックリスト #0歳 #赤ちゃん
この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)
フリーランス/埼玉県在住
発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。
子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功