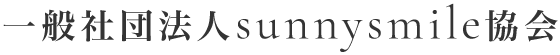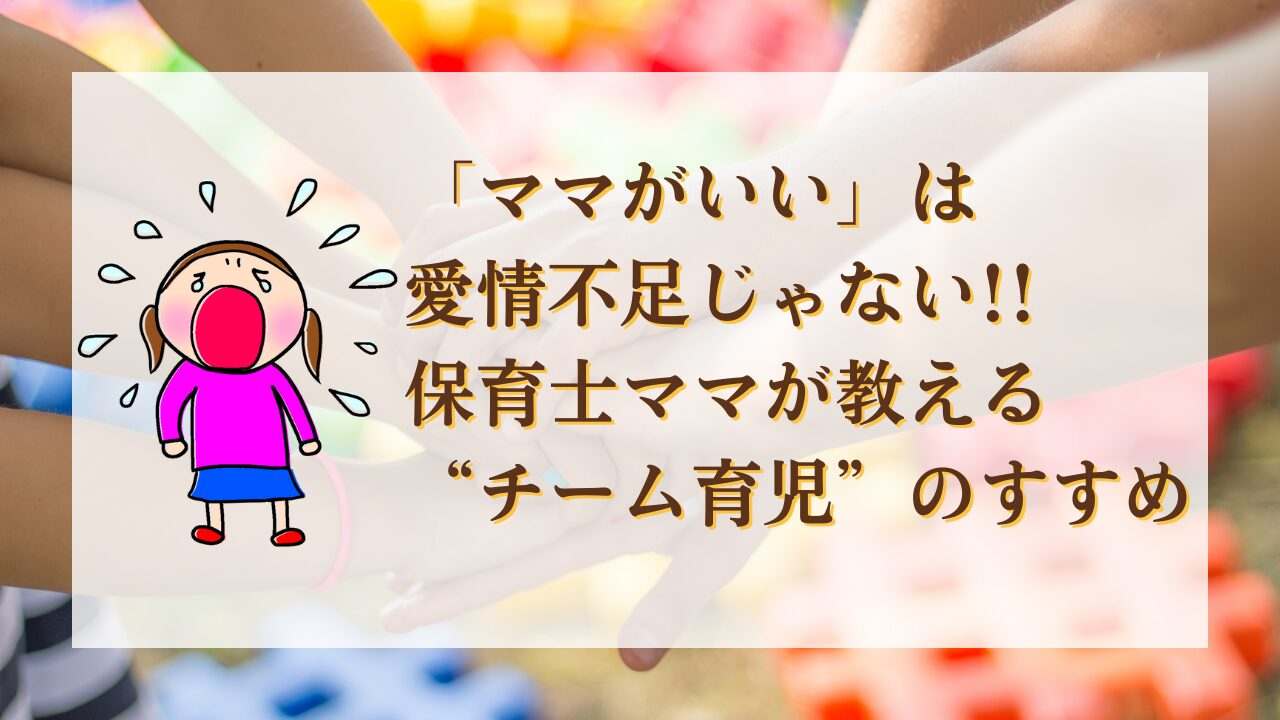ご飯を食べさせてもらうのもママがいい。一緒に遊ぶのもママがいい。何をするにも「ママがいい!」と言われ続けると、ママは嬉しいけれど…。パパがしょんぼりしたり、ママ自身も「私しかダメなの…?」「愛情がまだまだ足りないの?」と疲れてしまうこと、ありませんか?
はい、それ私です(笑)
でも実はこれ、愛情不足なんかじゃなくて、ママが子どもにとって“安心そのもの”だからこそ起きている現象なんです。ただ、この状態が長く続くとママはしんどくなってしまいますよね。今回は、そんな時に心が少し軽くなる子育てのヒントをお伝えします。
関連記事はこちら
夫婦仲が悪い女性の特徴10選!子供への影響と老後の心配は避けられない
子育てイライラ抑えられない理由と対処法!伝達エラー解消して笑顔の日々を取り戻す
子育てが思い通りにいかなくてイライラしているママへ。子どもとの笑顔時間が増えるヒントがここにあります。↓↓↓
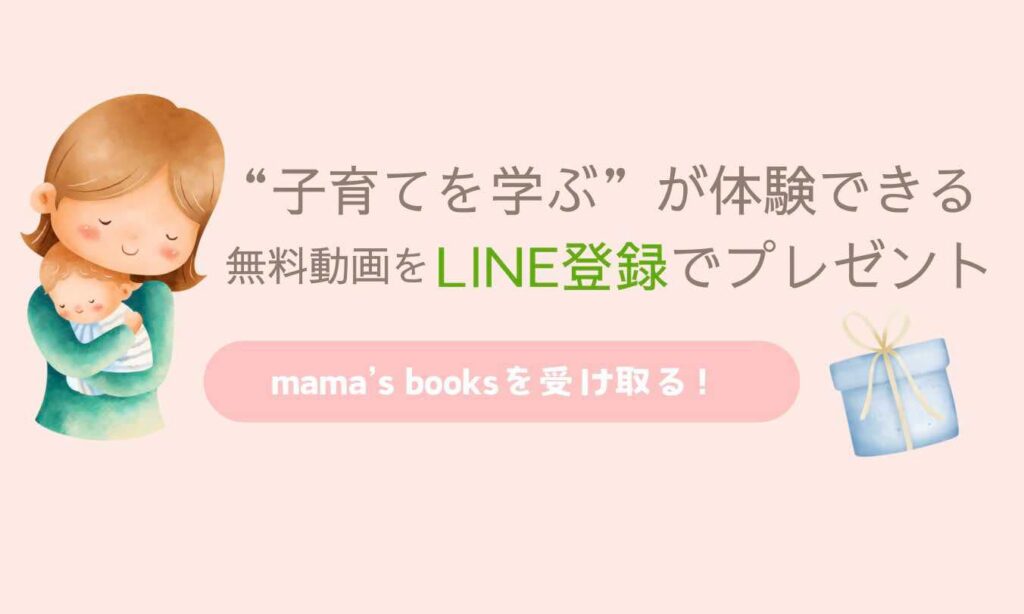
目次
「ママがいい」という子の特徴・言わない子の特徴
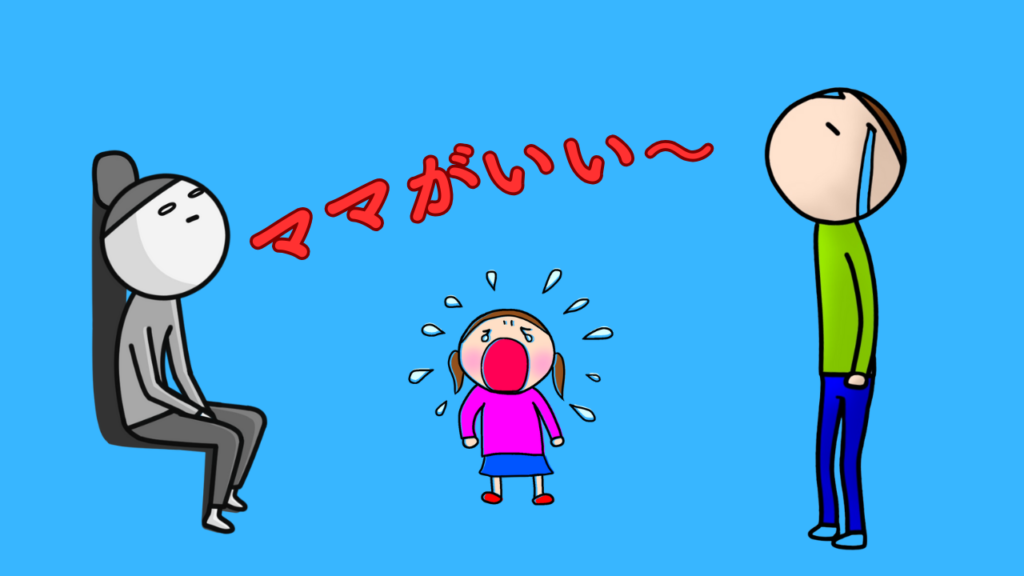
「ママがいい!」と甘えてくる子。 一方で、「ママじゃなくても平気そう」に見える子。どちらのタイプも、愛情が足りないわけではありません。 それぞれに、子どもらしい“安心の形”があるんです。
「ママがいい!」という子の特徴
このタイプの子は、ママへの信頼がしっかり育っている子です。 不安なときや新しい環境に向き合うとき、 自分の気持ちを素直に言葉にできる子です。
保育園でも「ママがいい〜!」と泣いて登園する子ほど、 保育園の環境にも慣れて安心できるようになるとスッと笑顔が戻ります。 それは、ママとの関係で“安心の土台”がしっかりできている証拠なのです。
ママが笑えば安心し、ママが不安そうだとドキドキする… そんなふうに、ママの表情がそのまま子どもの世界に映るんです。 つまり、「ママがいい」はママを信じているサインなんですね。
「ママがいい」と言わない子の特徴
一方で、「ママがいい」と言わない子もいます。 でも、それもまったく問題ありません。このタイプの子は、環境への適応力が高かったり、感情表現が控えめなタイプが多いです。ママがいなくても落ち着いて遊べるのは、 「ママはちゃんと帰ってくる」と信じているから。
保育園でも、「ママがいい」と言わない子が、 遊びの途中でふと玄関の方を見つめることがあります。 それは、「ママのこと、ちゃんと覚えているよ」という安心のサイン。「言葉に出す安心」もあれば、「心の中にある安心」もある。 どちらも、ママの愛情がちゃんと届いている証なんです。
番外編:「パパがいい〜!」と泣く子もいます
実は、保育園では「パパがいい〜!」と泣く子もいるんです。 そんなとき、保育士の私は心の中で思っていました。「あ、このお家はパパもしっかり関わってるんだな〜!」そうやって、勝手に“〇〇ちゃんパパ、子煩悩認定”してました(笑)。
パパがいい、と泣けるのも、 それだけ安心できる相手がもう一人いるということ。ママとパパ、どちらか一方ではなく、 「この人も安心できる」という経験が、子どもの心を強くしていきます。
ちなみに、わが家の場合は… 私がパパに指示を出してビシバシ鍛えながら、子育てに参加してもらっています(笑)。 でもそのおかげか、子どもたちはパパが大好き! 夫も少しずつですが、子どもとの関わりを楽しめるようになってきました。
『ママがいい“だけ”』になると起こりやすいこと
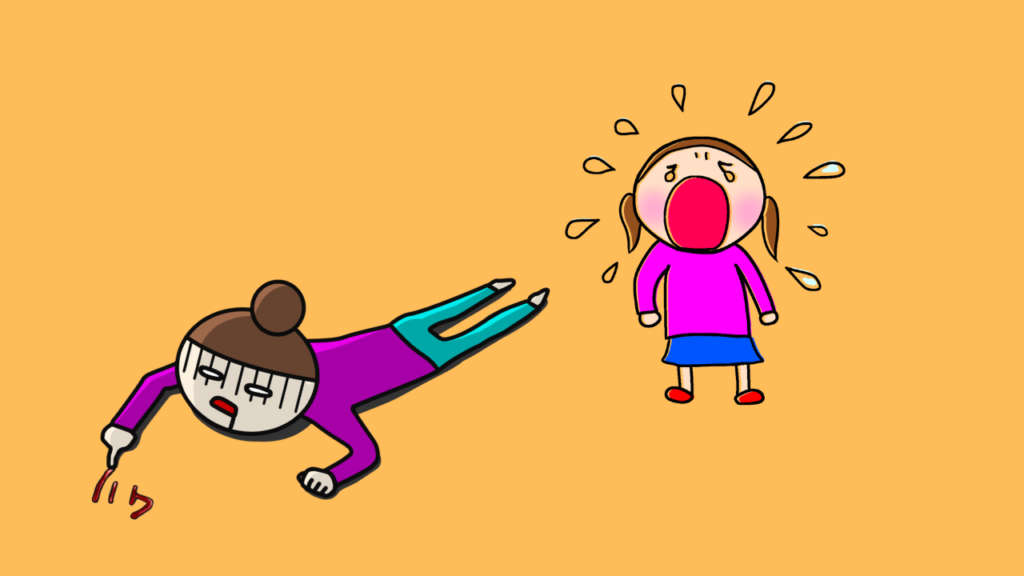
「ママがいい!」という言葉は、ママへの信頼の証ということは分かりましたね。 でも、ずっと“ママだけがいい”状態が続くと、少しずつママも子どもも疲れてしまいます。
ママがいないと泣き続ける、 パパが抱っこすると全力で拒否、 保育園でも離れられず登園が大変…。そんな様子に「どうしたらいいんだろう」と悩むママも多いのではないでしょうか。
でもそれは、ママが悪いわけでも、子どもがわがままなわけでもありません。
安心できる存在が“ママひとり”に集中しているだけなんです。
子どもの中には、「ママがいないと不安」という気持ちと、「ママがいると安心」という気持ちが共存しています。 だから、ママがいない=安心が消える、と感じてしまうんですね。
一方で、ママのほうも「私しかダメなんだ」と思うほど、 自分の時間がなくなって、気持ちが追い詰められていくことがあります。“ママがいいだけ”の状態を抜け出すポイントは、この「安心」を少しずつ“他の人にも広げていく”ことです。
ママが笑顔で過ごせる時間が増えると、 子どもは「ママがいなくても大丈夫かも」と感じられるようになります。 それが、自立への小さな一歩につながっていきます。
子育てが思い通りにいかなくてイライラしているママへ。子どもとの笑顔時間が増えるヒントがここにあります。↓↓↓
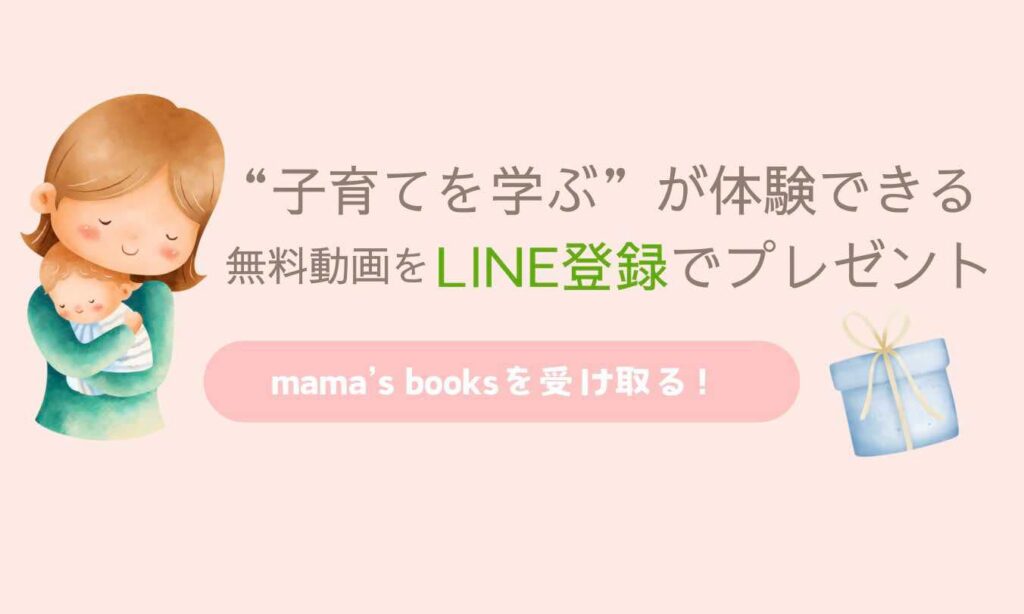
保育士ママが実践!「ママがいい期」の上手な向き合い方

「ママがいい!」という気持ちは大切にしながら、 少しずつ“ママ以外でも安心できる経験”を増やしていくことが、 ママにも子どもにも優しいステップになります。
ここでは、私が保育士として、そして一人のママとして意識している “安心を広げるための関わり方”をお伝えします。
① 無理に離さなくていい
「ママじゃなきゃダメ」と言われると、 つい「パパのところに行って!」と言いたくなる気持ち、よく分かります。 でも、無理に離そうとすると、子どもの中の不安が大きくなってしまうことも。
まずは「ママがいいんだね」と受け止めてあげることが大切です。 この“共感のひとこと”があるだけで、子どもは安心します。 そして「ママはそばにいるよ」と伝えながら、 少しずつ安心の幅を広げていきましょう。
② 安心できる“順番”を作る
いきなり「パパとやってみよう!」だとハードルが高すぎることもあります。 そんなときは、ママ→一緒に→パパという流れを意識してみてください。
たとえば、
- ご飯を食べるときは最初の一口だけママと、あとはパパと一緒に食べる
- お風呂は最初にママが入れて、後半をパパにバトンタッチして入浴する
少しずつ安心の順番を作ることで、 「ママがいなくても大丈夫」という気持ちが自然と育ちます。
③ ママが笑顔でいる時間を“優先する”
ママが笑顔でいられる時間は、子どもの心にとっても安心の栄養です。 「家事を完璧にこなすより、今日はゆっくりお茶を飲もう」 そんな時間こそ、子どもの安心を広げるチーム育児の第一歩。
パパや家族、支援サービスなどに少し頼ることも、 “弱音”ではなく“信頼を広げる練習”なんです。ママがホッとできる瞬間が増えると、 子どももその姿を見て、安心の輪を広げていけます。
「チーム育児」は“頼れる人を増やす”ことじゃない
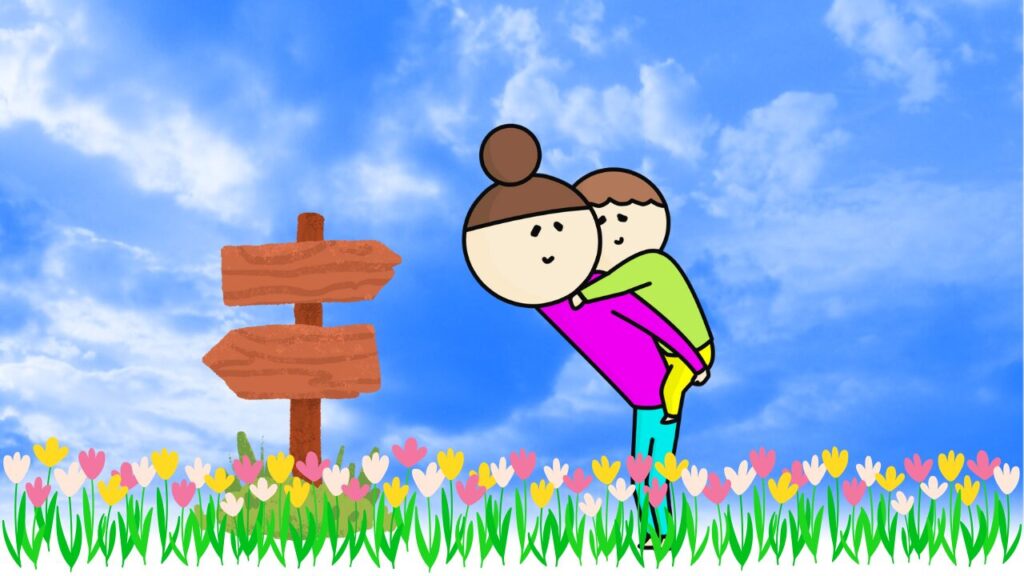
「チーム育児」と聞くと、“もっと人を頼らなきゃ”“協力してもらわなきゃ”と思うママも多いですよね。
でも実は、チーム育児って誰かを増やすことじゃなく、ママがひとりで抱え込みすぎない関わり方を選ぶことなんです。
ワンオペが当たり前になっているママにとって、「頼れる人なんていない」と感じることもあると思います。でも、“物理的に助けてくれる人”がいなくても大丈夫。
たとえば、
・子どもと一緒にごはんを作って「できたね!」と笑い合う
・祖父母とビデオ通話して、みんなで笑顔になれる時間をつくる
・ママ向けのオンラインコミュニティで気持ちを共有する
こうした小さな関わりも立派なチーム。誰かに手伝ってもらわなくても、“心が少し軽くなる瞬間”をつくることが、チーム育児のはじまりです。
チーム育児は、「助けを呼ぶ力」よりも「ひとりで頑張りすぎない選択」。ママが笑顔でいられること、それ自体が、子どもにとっていちばん安心できる環境なんです。
子育てが思い通りにいかなくてイライラしているママへ。子どもとの笑顔時間が増えるヒントがここにあります。↓↓↓
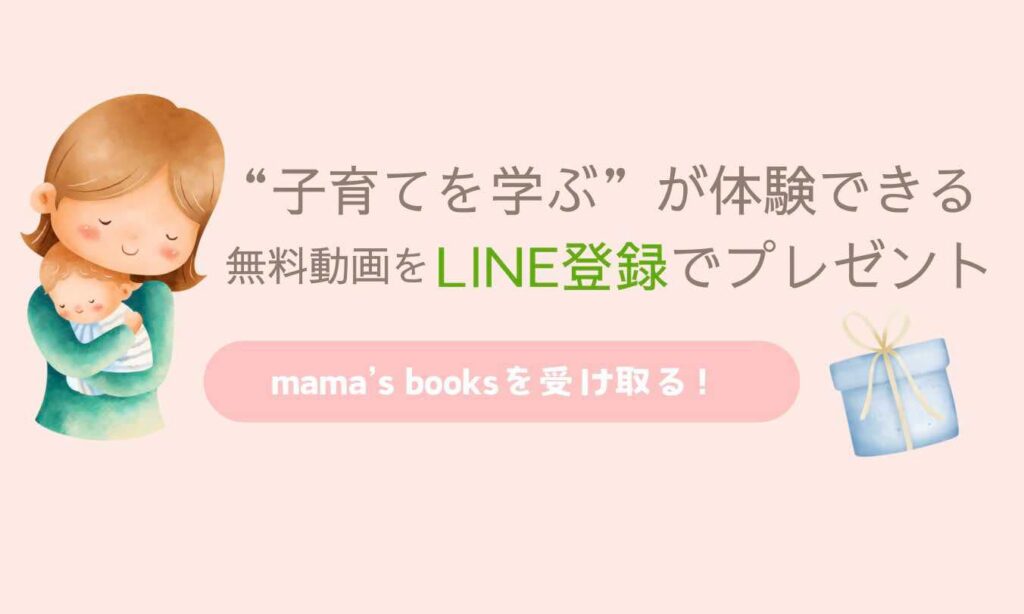
まとめ:「ママがいい」は信頼の証。だけど、ママも支えられていい

「ママがいい!」という言葉は、子どもがママを“世界でいちばん安心できる人”だと思っている証です。
それは、ママが日々たっぷりの愛情を注いできたからこそ生まれた信頼。
でも、その信頼をひとりで背負い続けるのは大変。だからこそ、「ママがいい」を受け止めながらも、
ママ自身も誰かに支えられることを許していいんです。パパや祖父母、先生、そして同じように頑張るママたち。少しずつ関わる人が増えていくことで、子どもの「安心の輪」も、ママの「心の余白」も広がっていきます。
ママが笑顔でいることは、何よりも子どもの安心につながる。“ママがいい”という言葉の奥には、「ママ、いつもありがとう」という想いが、ちゃんと隠れています。
世界中のママへ。今日も子どもたちに、“愛情という名のプレゼント”を届けてくれてありがとう!!
関連記事はこちら
子どもが野菜食べない諦めちゃダメ!野菜嫌い克服成功の秘訣とは
ワンオペ育児、うざいと思うあなたへの処方箋!言葉が生む亀裂とは
子育てのお悩みお気軽にどうぞ
 一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

ゆい(4歳男の子、3歳女の子)
3、4歳の年子ママ。保育士として1,300人以上の子どもたちと携わる。2人目の妊娠をきっかけに起業し、現在140人以上の働き方に悩むママたちと向き合う。仕事のモットーは「気持ちにまっすぐ」「頑張らないように頑張る」Instagramでは120%元気を取り戻せる夕食レシピを発信中!!
#ママがいい#愛情不足