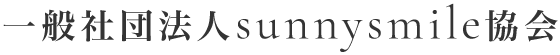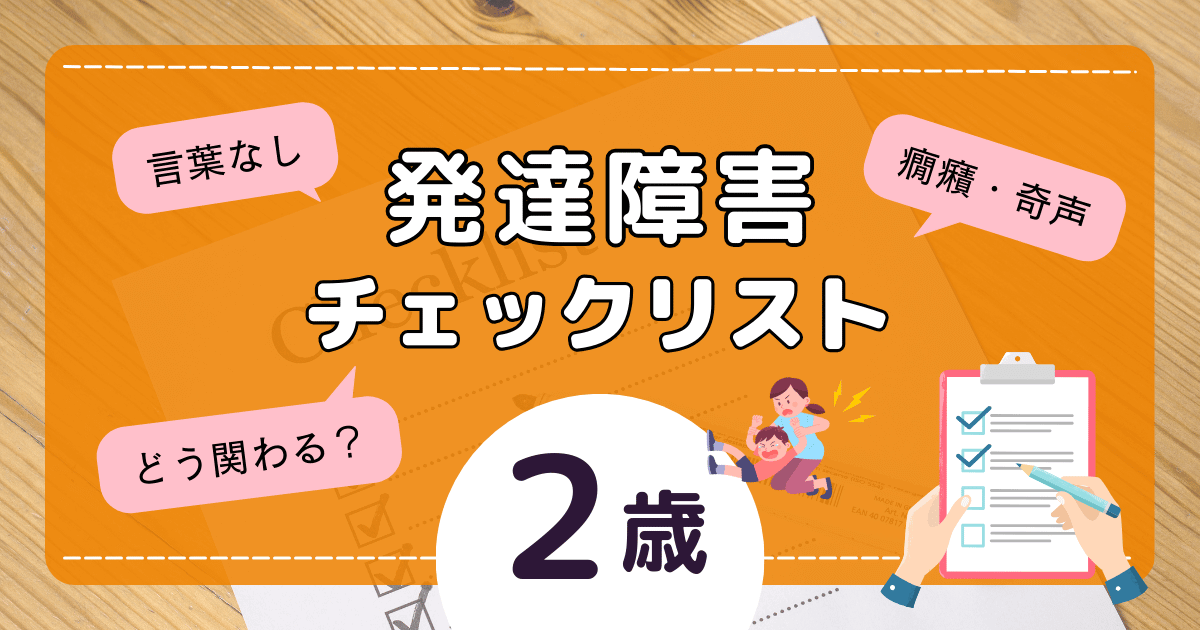2歳になると発達の差が大きくなり、つい周りの子と比べてしまうことってありませんか?
うちの子はまだ言葉が出てないのに、同じ年のお友だちはママとおしゃべりしてる…
癇癪が毎日続いて、もうどうしたらいいか分からない。正直、限界かも…
そんな気持ちになるのは自然なことだと思いますし、私自身も長女が2歳の頃は「もしかして発達障害?」と不安になった時期がありました。
長女は2歳の頃、本当に大変で――発語なし、癇癪、奇声、寝ない…何をしても言うことを聞かず、私も毎日イライラしてばかりでした。
「イヤイヤ期だから仕方ないよね」と思っていたのですが、1年後に育児を学んでみると、実は子どもではなく私の関わり方が原因だったと気づき、ものすごく後悔しました…。
この記事では、
- 2歳で見られる発達障害の特徴チェックリスト
- 私がしてしまった間違った対応
- 今からでもできる!2歳児の悩み対処法と発達を伸ばす関わり方
についてまとめています。
「子どもの癇癪や言葉の遅れ、どうしたらいいの?」と悩んでいるママに、少しでもヒントになれば嬉しいです!
また、記事の最後には育児書やネット情報では、子どもの発達遅れの悩みを解決できなかったのに、「ある方法」を使ったらすぐに解決できた!
その秘密についてご紹介しておりますので、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
関連記事→ 2歳児のイヤイヤ期に疲れた…年子ママがたどりついた究極の関わり方
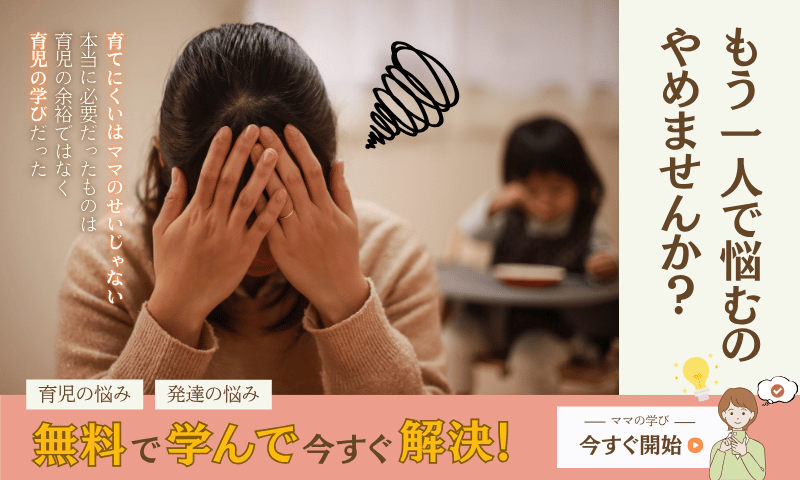
目次
2歳の奇声や癇癪は発達障害のサイン?|発達障害の特徴・チェックリスト

2歳は言葉が急速に伸び、自分で身支度をしたり、自立に向けて歩き始める時期です。
でも、「言葉が出ない」「自分から何もしない」と感じると、他の子と比べて心配になりますよね。
私の長女の体験や発達支援資料をもとに作成した、2歳の発達障害チェックリストはこちらです。
| □ 2語文がなかなか出ない |
| □ 名前を呼んだり、呼びかけに対して反応しない |
| □ 目を合わせにくい、表情が乏しい |
| □ 激しい癇癪を起こす |
| □ 同じ動きを繰り返す(常同運動) |
| □ 特定の物や順序に強くこだわる |
| □ 偏食が強い(食感・色・匂いに敏感) |
| □ 音や光に過敏/鈍感な反応をする |
| □ お友達と遊ばず一人遊びを好む |
| □ 人見知りをしない(他人への関心が薄い)もしくは人見知りが激しい |
長女は2語文が出たのは2歳半過ぎ。発語がほとんどなく、お友だちとも遊びませんでした。
偏食やこだわり、癇癪にも悩んでいたので、チェックリストにはほぼ当てはまっていました。
ただ、特徴が当てはまったからといって、必ずしも発達障害とは限りません。
2005年に施行された発達障害者支援法では、発達障害は「脳の機能障害」と定義されています。そのため「先天的なものだからママの育て方のせいではない」「治すものではない」と一般的に認識されているかもしれません。
2歳の時点では、脳も体も未発達な部分が多く、個人差の範囲なのか、発達障害によるものなのかの判断は難しいです。
大切なのは、チェックリストは診断の目安ではなく、あくまで気づきのきっかけだということ。
言葉が遅くても、3歳頃に急に話し始める子もいますし、こだわりが強い子も成長とともに落ち着くことがあります。
今後の親の関わり方やサポートで、改善できることはたくさんありますよ!
【経験談】2歳で言葉なし・癇癪多発…発達障害長女に間違った対応をした結果

2歳はイヤイヤ期真っ盛り…ママもイライラしたり、ついキレてしまうことがありますよね。
私も長女が2歳の頃、無視されたり拒否される度に、「ちゃんと聞いて!」とキレて教えていました。
当時は「長女のため」と思って厳しく接していたのですが、1年後に子育てコーチングを学ぶと、それが長女の発達を阻害していたと知って後悔しました。
ここからは、私の実際の経験と学び、そして当時の後悔を踏まえて、育児の間違った対応とその結果についてご紹介します。
間違った対応① 激しい叱責
イヤイヤ期で全く言うことを聞かない子に、「ちゃんと聞きなさい!」と激しく叱責する。
たとえその場では従うことができても、怖くて泣きながら従っていたので、本当の理解にはつながっていないことが多いです。
私の長女は(後から分かったことですが)聞いて理解することが苦手でしたので、怒られた理由が全く理解できず、同じ間違いを何度も繰り返してばかりいました。
その度に「何度言ったら分かるの?」と繰り返し怒っていたのですが、怒るたびに泣いて酷い時には癇癪を起こしていました。
結果的に、激しい叱責は長女を苦しめるだけでプラスの効果は一つもなかったのだと、今も後悔しています。
間違った対応② 言うことを聞かないと恐怖で支配
私はかつて、言うことを聞かない長女に対して、「鬼の電話」というアプリを使っていたことがあります(ちなみに結構怖いです…)。
言うことを聞かせる、というよりは「ただ怖がらせる」だけで、例えその場では従ったとしても根本的な解決にはなりませんでした。
むしろ子どもの不安を強めてしまい、恐怖で子どもを支配してしまい、信頼関係を損ねてしまう結果につながったのです。
「怒られるからやる」のではなく「自分の意思で」物事に取り組んでもらいたいですよね…
私もそう思い、私は子育てコーチングを学んでからは「鬼の電話」のアプリを削除しました。
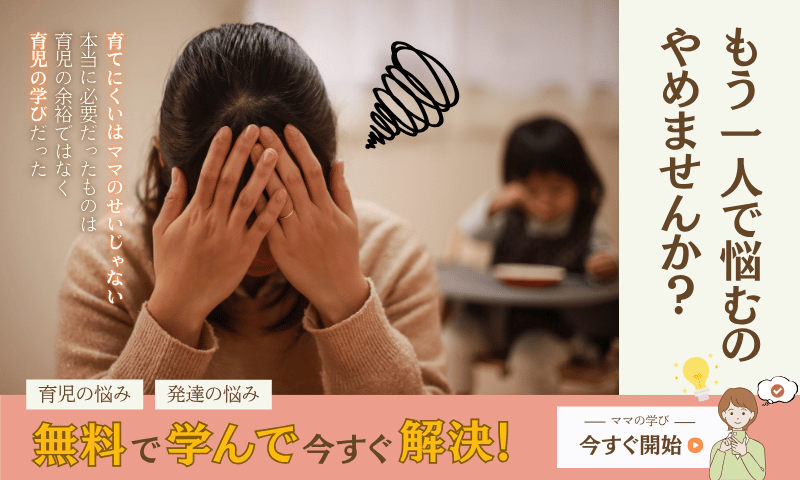
間違った対応③ 突き放す
私の長女が癇癪を起こして泣きわめいた時、収拾が全くつかずに「もう知らない!勝手にして!」と突き放してしまったことが何度もありました。
あるいは、何かやってほしくて甘えてきたときに「自分でできるでしょ」と冷たく返してしまったことも…
一見「自立を促している」ように見えますが、実際には「ママは助けてくれない」と子どもに感じさせ、安心感を奪ってしまう対応でした。
突き放された子どもは「困ったときに頼れない」と思い込み、余計に癇癪や反発が強まる要因になってしまうことがあります。
長女も私が何度も突き放したせいで、人に助けを求めるのが苦手な子になってしまい、1人で何とかしようと無理をして、上手くできないとすぐ癇癪を起こす子になってしまいました。
結論:【できる子】にならず【自信のない子】に成長…
長女は1年後に発達障害だと診断され「言われたことを聞いて覚える」「自分の思いを言葉にするのが苦手」なことが分かりました。
そのため、これまで口頭で教えてきたことは理解ができず、全く身につけることができなかったのです。
ただ今まで怒り続けたことで、長女に残ったのは「叱られた=恐怖」という記憶だけで、親子関係も少しギクシャクしてしまい、長女は私に対してどこか怯えるようになり、ママを呼ぶ回数も減ってしまいました。
その後:子育てコーチングで【自己肯定感】を育て長女は【自信】を取り戻す
私が怒り続けたことで、長女は自信のない子になってしまい、何かやらせようとしても失敗したり叱られるのを恐れてしまい、自分から何かを取り組めない子になってしまいました。
そんな長女の発達について悩み続けて1年後、私が出会ったのが【子育てコーチング】でした。
子育てコーチングを学んで、自分のこれまでの育児を見直し、長女の自己肯定感を取り戻すのに尽力しました。
その結果、長女との関係が少しずつ改善し、5歳になった今では何でも話してくれる関係になるほど【親子の絆】を育てることができました!
もし子育てコーチングを学んでいなかったら…長女は今も自信のない子のままでいたのかもしれません。
私が長女の自己肯定感を上げるために実践した、【子育てコーチング】についての詳細はこちら↓
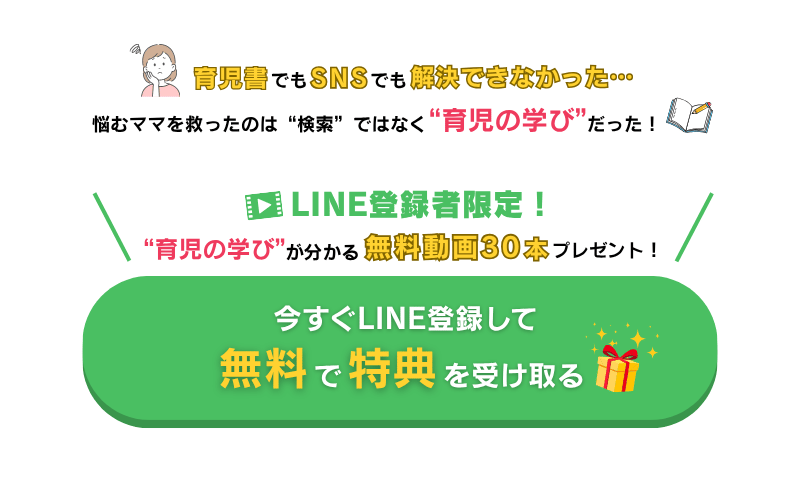
2歳の発達悩み|ママの経験から学ぶ対処法5選

2歳の子どもは、自我が芽生えてきて自己主張も強くなる時期です。
「どうしてこんなに癇癪を起こすの?」「言葉が遅いのはうちの子だけ?」と悩むのは、他のママも同じだと思います。
私自身も長女の発達に戸惑ったり、何度も心配になった経験があります。
ここでは、実際に私が向き合ってきた悩みと、その中で学んだ対応法をご紹介します。
悩み① 癇癪
スーパーや公園で突然癇癪を起こし、大泣き・大暴れされると、本当に困りますよね。
私も最初の頃は「静かにして!」と叱りつけて止めていましたが余計に騒いでしまい逆効果に。
実は癇癪は子ども自身も止め方が分からず、無理に止めようとすると余計パニックになりやすいので、癇癪時は「止めようとする」のではなく、「気持ちを言葉に代弁する」のが大切です。
癇癪時の声かけの例がこちらです。
- 「遊びたかったんだね」
- 「まだ帰りたくなかったんだね」
- 「これから夕飯だから、また明日遊ぼうね」
ただあまりにも激しい時は、声かけすら拒否してしまうので、そう言う時は落ち着ける場所に避難し、時間が過ぎて落ち着くのを待ってから声をかけてあげると子どもも安心します。
悩み② 奇声
突然大きな声を出す姿に、周囲の視線が気になって焦ることもありますよね…
私の娘も、不満が溜まった時や嫌なことがあった時に「キーーー」「アーーー」と大きな奇声をあげることがよくありました。
スーパーで奇声をあげられたこともあり、周囲の人たちが驚いて私と長女が注目されてしまい、私は恥ずかしい思いをしたことも…
そんな奇声の対応のコツは「静かにして」と注意するのではなく「環境を整えること」です。
- 人が多い場所は長時間過ごさない
- 好きな音楽やおもちゃで気持ちを切り替える
- 迷惑にならない場所で落ち着かせる
奇声も癇癪と同様に、子供が自分で止めるのは難しいため、親が騒ぎを起こさない環境、もしくは騒いでも大丈夫な環境を作ってあげるのが安心です。
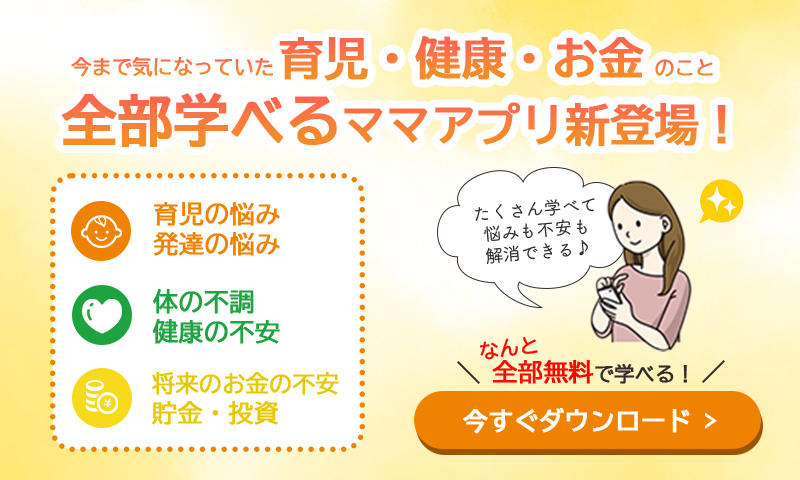
悩み③ 言葉が出ない
「2歳になってもあまり喋らない…」と焦る気持ち、よく分かります。
私も長女が小さい時は特に気にしていて、なるだけ会話を増やすよう意識していたのですが、あまり効果はなかったように感じます。
そんな言葉の遅い子ですが、無理に教え込むより、「言葉に触れる環境を整える」と「視覚化」がポイントです。
- たくさん語りかける
- 絵本の読み聞かせ
- 興味のある絵本、図鑑、たった1ページだけでもOK!とにかく続ける
言葉を聞くのが苦手な子でも、絵本として「見せて聞かせる」方法であれば、「視覚」で言葉を吸収することができます。
目で見て、耳で聞いて、五感で言葉に触れる環境に居続けることで、言葉に興味を持ったり、語りかけに少しずつ耳を傾けてくれる日がいつかやってきますので、それまでは子どものペースで見守ってあげてください。
もっと多くの経験談を知りたい方はこちらの記事もおすすめです ↓
悩み④ 寝ない
夜遅くまで遊びたがったり、夜泣きで何度も起きたり…親は寝不足で本当に辛いですよね。
私の長女も寝つきが悪く夜9時を過ぎても寝ないことが多く、それでも朝は平日・休日関わらず5時半起き…親は早朝に起こされ続けていたので本当に辛かったです。
我が家では「寝る前のルーティン」をつくることで改善しました。例として
- 夜8時 → 絵本を読む
- 電気を暗くする
- 好きなぬいぐるみとベッドへ
言葉の理解が遅い子には、口頭よりもスケジュールボードで視覚化すると理解しやすくなります。
そして、1つでもできたら必ず褒めて、少しずつ「寝る前のルーティン」を習慣化していくことで、自然と寝れる状態に近づいていきますよ。
視覚化に便利なスケジュールボードについての詳細はこちら↓
悩み⑤ 言うことを聞かない
「こっちに来て!」と呼んでも走り回る、「片付けて」と言っても無視…。2歳児にはよくあることですが、ママにとっては大きなストレスですよね。
声をかけても無視されるのはストレスですが、過度に叱らず、反抗を「成長のため」と受け流す方がママも楽です。
それでもどうしても話を聞いてもらいたい時は、突き放したり、激昂したりせず、「どう聞いたら、言うことを素直に聞いてくれるか?」を子どもの様子を見ながら探ってみてください。
声かけ例としては、
- 長女(真面目タイプ):「手伝ってくれるとママ助かるな〜!やってもらえる?」
- 次女(かまってちゃん):「次女ちゃんやらないなら、マイメロちゃん(ぬいぐるみ)にお願いしていい?」
私の長女と次女は性格が全然違うため、効果のある話しかけ方は異なります。
長女は真面目で親の期待に応えたいタイプなので、「やってくれるとママは嬉しい」という声掛けをしています。
反対に次女は甘えん坊なかまってちゃんタイプ(現在イヤイヤ期)で、話を「やだ」と突っぱねてきたら「いいよ、じゃあ別の子にお願いするけどいい?」という感じの声掛けをすることが多いです。
自分の子どもの性格を見て、どう声をかければ動いてくれるのか、子どもの様子を見ながら色々試してみてくださいね。
そして、大事なことは「やりなさい」ではなく「やってくれる?」のスタンスで声をかけることです!
「やれ!」と命令されると相手に対して反感を持つのは、大人も子どもも一緒なんです。
もし無意識に命令口調になっているママは、まずはそこから改善していきましょう。
有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?
【結論】手のかかる2歳児への対応|発達を伸ばすカギはママの関わり方にあった
イヤイヤ期で手のかかる2歳児ですが、それは自立のための準備をしている段階とも言えます。
そんな子どもの自立を促すために欠かせないものが「ママの関わり方」です!
- 癇癪や奇声は「止める」のではなく「気持ちを受け止める」ことが大事
- 言葉の遅れは焦っても好転しない、「語りかけ」「絵本の読み聞かせ」で環境を整えてあげる
- 寝ない子には「毎晩同じルーティン」で安心感を与える(視覚化するとより効果が高い!)
- 言うことを聞かないときは「叱るより褒める」を意識すると変わっていく
- どんな悩みも「成長の途中だから大丈夫」と自分に言い聞かせながら、子どものペースで寄り添うことが一番
イヤイヤ期の2歳児の発達を伸ばすために大切なことは「周りの子の発達と比べないこと」「子どもに寄り添い、気持ちを受け止めること」です。
ママの関わり方を変えるだけで、子どもは安心してぐんぐん成長していけるものです。
他の子どもたちと比較するのではなく「昨日よりできたこと」を一緒に喜んでいけば、子どももママも少しずつ楽になっていきます。
完璧じゃなくてもいい、ママが子どもを大切に思う気持ちこそが、発達を促す栄養になるのです。
手のかかる子どもでも発達は伸ばせる?sunnysmile協会で実践法を学ぼう!
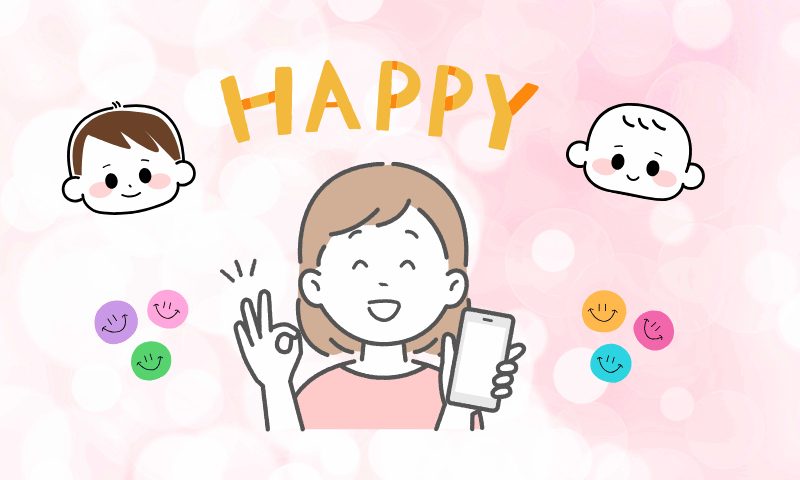
私の長女は発達障害のため周りの子たちよりも比べて苦手な物事が多いのですが、毎日生き生きと過ごせています。
その秘密は、ママが子どもの能力を伸ばすための育児を学び、子どもに合った育児法を実践しているからなのです。
長女が3歳の時に「己育て」「発達に合わせた子どもとの関わり方」を学んだのですが、学びを日常生活に取り入れたことで、自信を失った長女の自己肯定感を上げることに成功しました。
己育てを勉強する前は何事にも消極的だった私の長女でしたが、5歳になった今は自らダンスを習うことを決めて、毎日楽しそうに練習しているほど自分に自信のある子どもになりました。
- 年齢別に合わせて発達を促す方法
- 自分の子どもの性格に合わせた関わり方
- ママのイライラを減らす方法
など、他にも学べることがたくさんあって「学んだら育児がより楽しくなった」と思える発見がたくさんありました。
「興味がある」と思ったママ、その愛情あふれる働きかけが、きっと子どもの成長につながります。
こちらからぜひチェックしてみてください↓
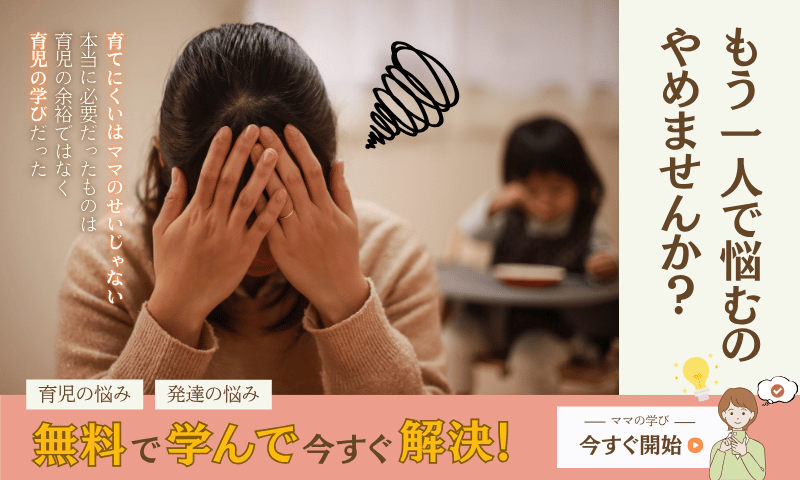
まとめ
この記事を通して、2歳の子どもの育児に悩むママにお伝えしたいことはこちらです。
- 子どもの成長は「ゆっくり」でも「違う形」でも、その子なりに必ず進んでいる。
- 2歳の発達のスピードは様々。「発達障害かも…」と悲観したり比べる必要はない。
- 今できないことがあっても、ママの関わり方次第で悩みは解消される!
- 「一緒にできたね」「ここまで頑張ったね」と声をかけるだけで、子どもの自己肯定感はぐんと伸びる。
- 完璧なママじゃなくても大丈夫。「寄り添う気持ち」こそが最高のサポートになる。
2歳の発達のつまずきや癇癪があると、「育て方が悪かったのかな」「発達障害かも…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれませんが、それは決して「ママのせい」ではありません。
むしろ、悩んで調べて、こうして向き合おうとしていること自体が、もう立派な愛情の証です。
子どもは必ず、自分のペースで育っていきます。「ちょっと遅いかな?」と思う今も、ママの優しい声かけや笑顔があれば十分。
ママが見守ってくれていることが、子どもにとって一番の安心であり、最高の成長の栄養になります。
どうか一人で抱え込まず、「大丈夫、きっと育っていく」と信じてあげてくださいね。
子どもとの関わり方に悩むママにはこちらもおすすめ ↓
#発達障害 #2歳 #癇癪 #言葉なし
 一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)
フリーランス/埼玉県在住
発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。
子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功