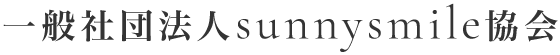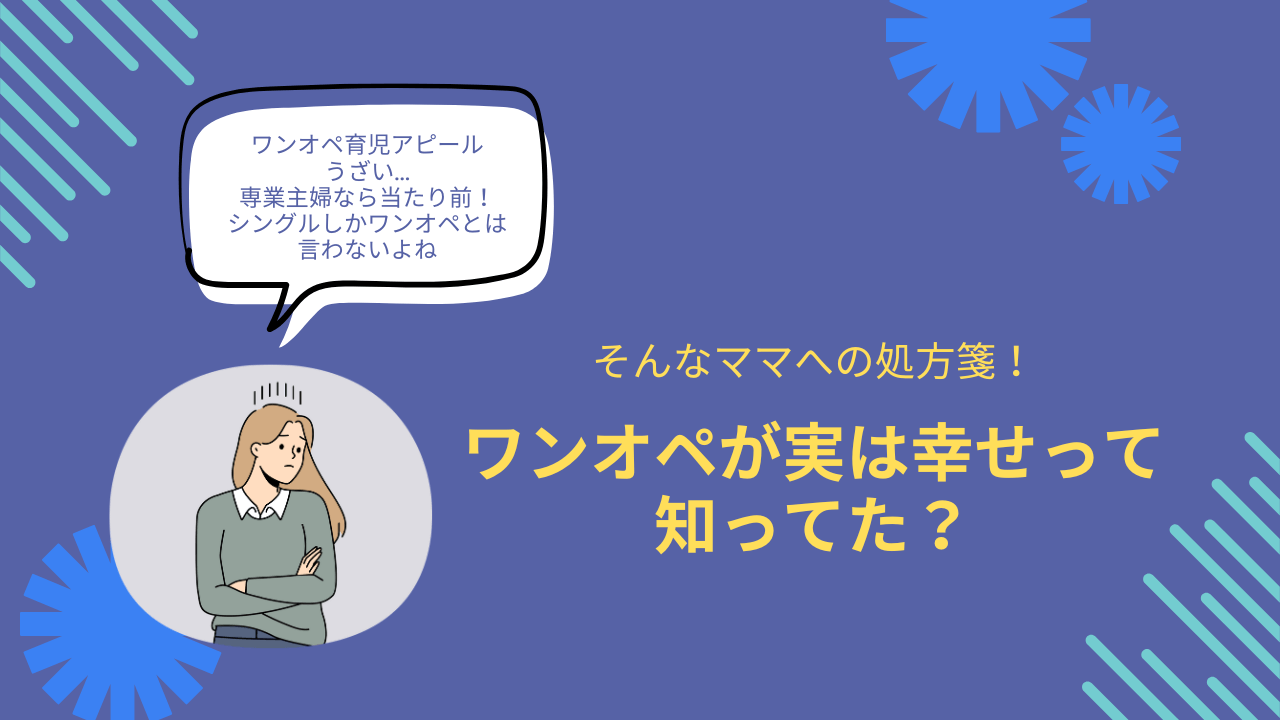パパがいない間、ママが1人で子供の世話をすることを「ワンオペ育児」とよく言いますよね。
最近、SNSや周りのママ友の投稿でよく目にすることも多いです。でも、正直なところワンオペ育児アピールって、見ていてうざいなと思うことはありませんか?
「一人で子育ては大変!」「私頑張ってるの!」とアピールしたい気持ちは分かりますが、時にはちょっと過剰に感じることもありますよね。
そんなママに向けて、ワンオペ育児にまつわる本音や気持ちが楽になるヒントなど以下のことをお届けします。
- ワンオペ育児アピールうざい…エピソード集
- ワンオペ育児という言葉から生まれた亀裂
- ワンオペ育児って実は幸せ!
最後まで読むことで、ワンオペ育児に対する考え方が変わり、アピールに対するイライラが消えること間違いなしです!
子育てのイライラを手放す方法はこちら→【経験談】子育てのイライラやばいワケ!解決策全て撃沈→夢のストレスフリー育児実現ナウ – 一般社団法人sunnysmile協会
子育てに関するイライラを減らせた!私が救われた子育て方法を無料で公開中♡
LINE登録で30本動画無料プレゼント中!
子育て・働き方に悩むママ必見!mama’sbookを受け取る
目次
ワンオペ育児アピールうざいよね…専業主婦の甘えに聞こえて何かイラつく
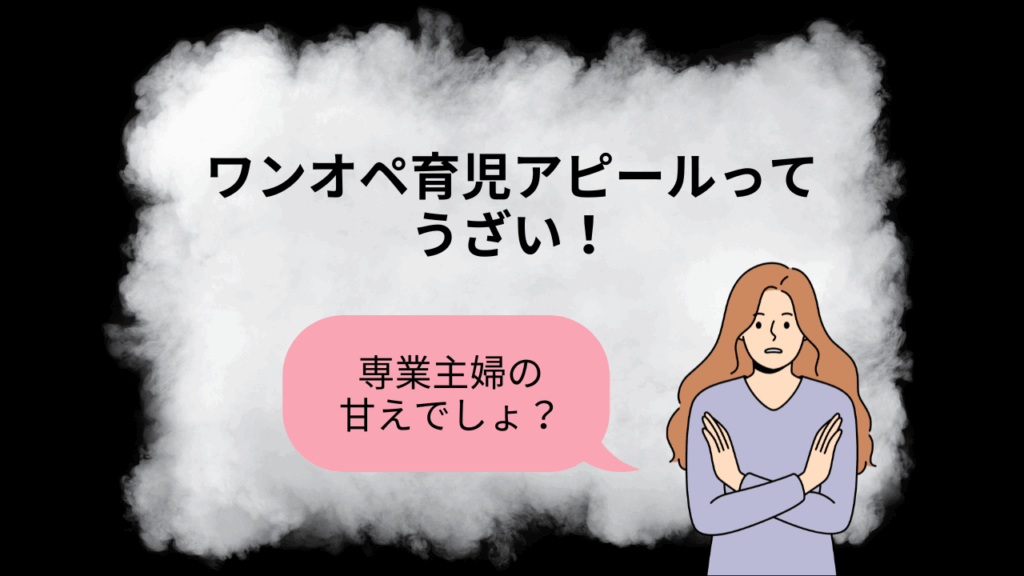
ネットやSNSを調査した結果、「ワンオペ育児アピールうざい!」と思われてしまうママの特徴と、うざいと思っているママの特徴がありました。アピールしているつもりはなくても、うざいと思われてしまうのは、専業主婦もしくは手助けがあるのにワンオペと言っているママ。うざいと思っているのは、ワーママが多いということです。
以下で私の意見も交えて詳しくお伝えします。
ワンオペ育児アピールを私はうざいと思わないけれど…
私は正直、ワンオペ育児アピールがうざいとは思いませんが、なぜアピールをしているのかが理解できません。
私のママ友にもいるんです。「今日はワンオペだ~。旦那が帰ってこないからさ。」と
言うママ。私は「あ、そうなんだ。頑張ってね。」と返事をしますが、「なぜ私にワンオペ育児アピールをするのだろう?」と考えてしまいます。
きっと以下のような理由があるのだろうと思います。
- 一人ですべてをこなすのが大変だから共感してほしい
- 一人で頑張っていることを褒めてほしい
- ただ誰かに愚痴を言ってスッキリしたい
- 育児に疲れている
しかし、ワンオペ育児をアピールするのではなく、子育てが大変だということを相談してくれたら素直に共感ができるのにといつも思っています。
アピールしているつもりはなくても、うざいと思われているかもしれないということを考えると、話すときに慎重になってしまいますね。親友くらいに仲の良いママ友であれば、何でも気軽に話せるのですが、保育園や近所など絶妙な距離のママ友には、アピールしないように気を付けたいものですね。
専業主婦でワンオペ育児アピールってうざい
SNSやネットの情報を調査すると、専業主婦のママが「ワンオペ育児辛いよ」などと投稿しているのに対して、他のママが「うざい」と感じイライラしているようです。
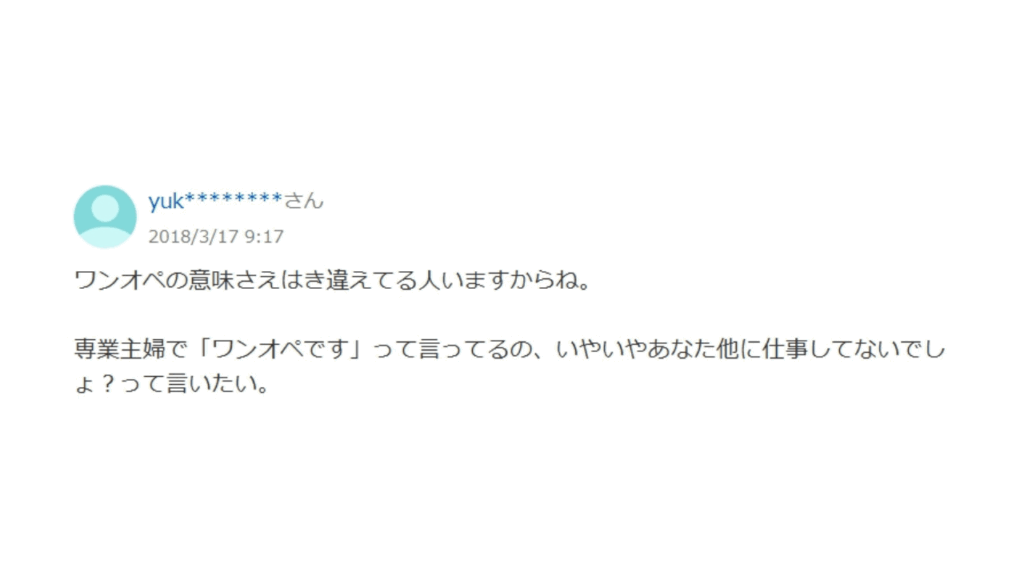
❝ワンオペの意味さえはき違えている人いますからね。専業主婦で「ワンオペです」って言ってるの、いやいやあなた他に仕事してないでしょ?って言いたい。❞
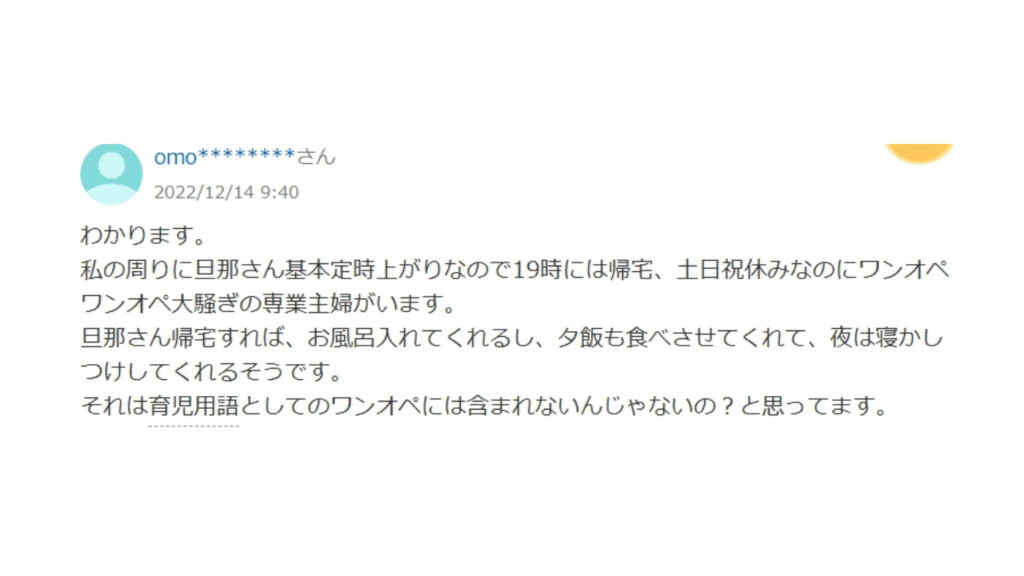
❝わかります。私の周りに旦那さん基本定時上がりなので19時には帰宅、土日祝休みなのにワンオペワンオペ大騒ぎの専業主婦がいます。旦那さん帰宅すれば、お風呂入れてくれるし、夕飯も食べさせてくれて、夜は寝かしつけしてくれるそうです。それは育児用語としてのワンオペには含まれないんじゃないの?と思っています。❞
確かにシングルマザー、パパがほとんど自宅にいないなどの本当にワンオペ状態のママやワーママから見ると、専業主婦や全然ワンオペではないママの投稿はうざいと感じますよね。
専業主婦ママのワンオペ育児アピールがうざいと思う理由はいくつかあり、まとめると以下のようになります。
- 専業主婦で仕事をしていないのに「1人で子育てしている」とアピールするのが変。専業主婦なら当たり前では?
- 朝も夜も休日もパパが家にいて、それ以外の時間を「ワンオペ育児」と表現している。それはただパパが不在なだけでは?
- 本当のワンオペ育児はシングルマザーとか単身赴任の奥様では?それ以外でワンオペ育児と言うママは甘えている。
まとめるとそれほどワンオペでもないママに対して本当にワンオペ状態のママがうざいと感じています。つまり自分よりも余裕のある子育てをしているであろうママに対して、「自分の方が大変だ!」という感情が湧くとうざいと感じると想定できます。
ただ、専業主婦だからワンオペでも我慢しろ、というわけではありません。「私一人で子育てしてるの~!頑張ってるでしょ~!」と言うようなアピールをすること自体が良く思われないのです。
イライラするママ友とはどう付き合ったらいいの?→ママ友疲れる…原因と上手な付き合い方!ストレスにならない方法とは – 一般社団法人sunnysmile協会
新登場!育児に悩むママのためのアプリ!全国のママと育児相談もできちゃうよ♡
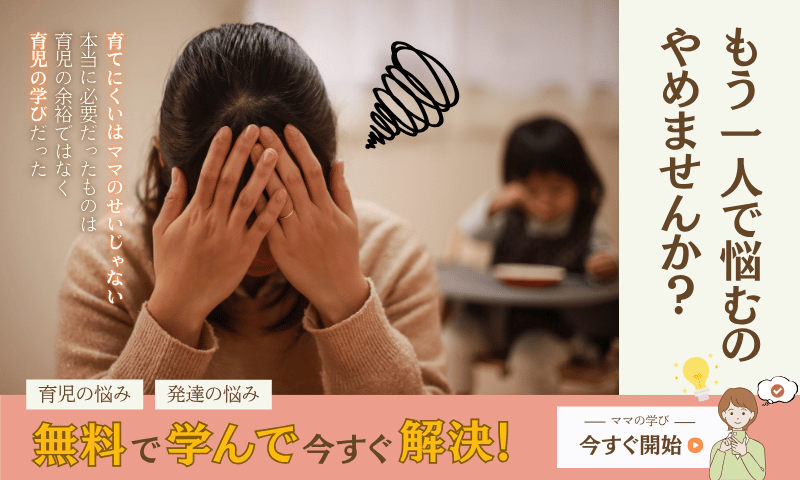
【処方箋】もう、うざがらない!子育て仲間だもん。ワンオペ育児という言葉から生まれた亀裂を理解する
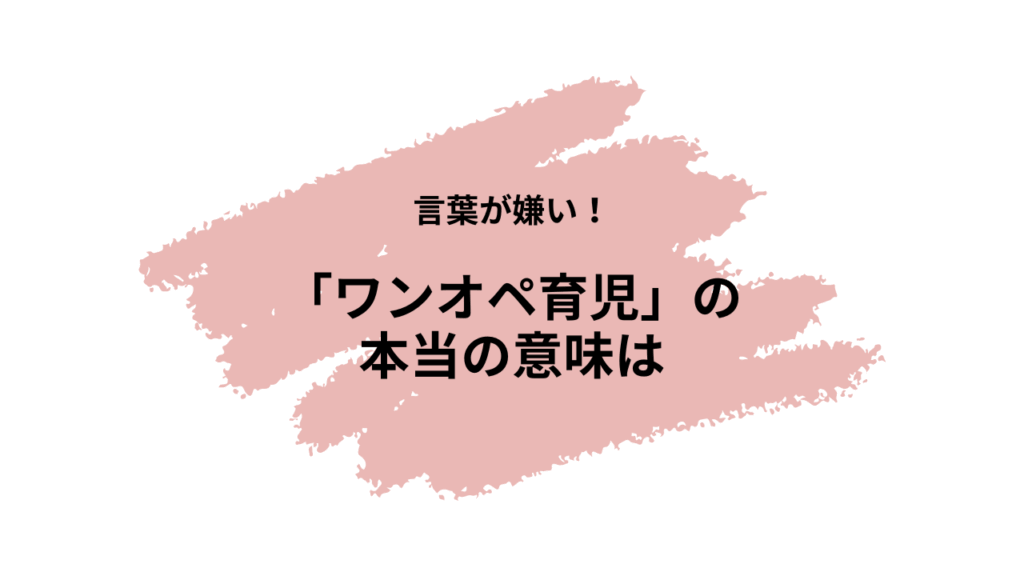
ワンオペ育児という言葉のせいで、ママたちの間に亀裂ができてしまっています。
本来のワンオペの意味、知っていますか?ママ同士で認識が違うということが「うざい」と感じる要因にもなっています。以下で詳しくご説明しますね。
ワンオペ育児ってそもそもどんな状態?
ワンオペという言葉は、ワンオペレーションの略称で、2014年に某大手飲食チェーン店の深夜時間帯のスタッフが、1人だったことが発覚した時に誕生した言葉です。
ワンオペ勤務の大きな問題点として挙げられているのは、以下のようなことです。
- トイレに行けない
- トラブル対応できない
- 休憩できない
- 疲れがむやみにたまる
休みたいと思っても、スタッフが自分しかいないので休むことができません。その過酷な労働環境が大きな社会問題になりました。
そこから派生して、育児をママに任せっきりにすることを「ワンオペ育児」と言うようになりました。
- シングルマザー
- パパが単身赴任
- パパが激務でほとんど顔を合わせない
- パパがいるのに家事育児を一切してくれない
こういった状況をワンオペ育児と呼んでいる人が多いですね。
確かに、子供が赤ちゃんの頃は自分の好きなタイミングでトイレに行ったりご飯を食べたりできなかったから、過酷と言えば過酷だった…。
目を離したり放棄してしまったらトラブルが起きかねない状況では、自分が我慢をするしかなく、心身が疲れるのも無理はありませんね。
ワンオペ育児と言う言葉から生まれた亀裂
ワンオペ育児という言葉自体が嫌い、気持ち悪いと感じている人も少なくありません。
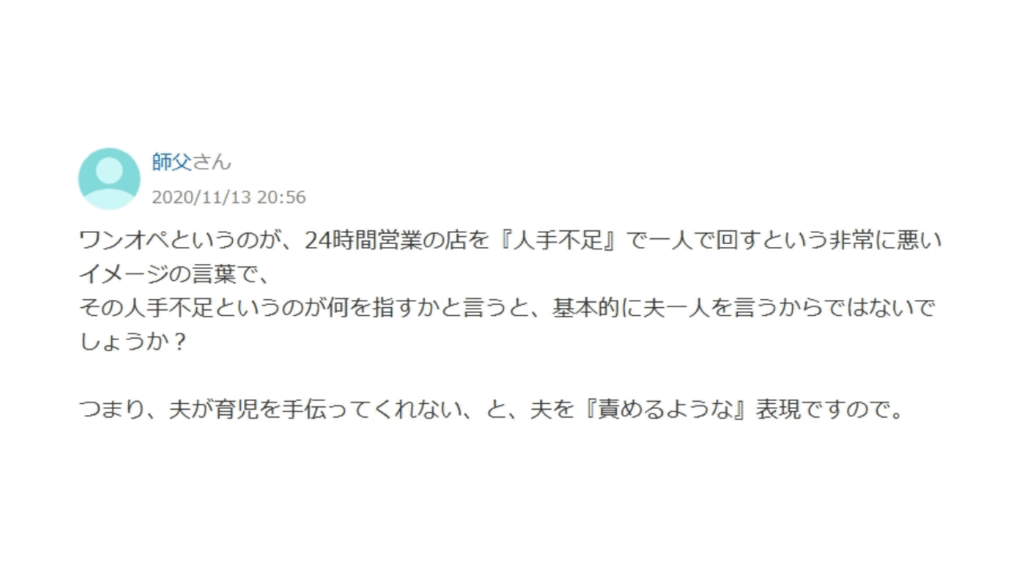
❝ワンオペというのが、24時間営業の店を『人手不足』で一人で回すという非常に悪いイメージの言葉で、その人手不足と言うのが何を指すのかと言うと、基本的に夫1人を言うからではないでしょうか?つまり、夫が育児を手伝ってくれない、と、夫を『責めるような』表現ですので。❞
「夫がいないせいで」「夫が家事育児しないせいで」ワンオペ状態というイメージになってしまい、よく思わないママもいます。仕事が多忙で家事育児に参加したくてもできないパパもいますし、家族のために仕事をしているのですから、何もしていないわけではありませんよね。
そういった考えの違いからも、ワンオペという言葉を使うママと使わないママとの間で、亀裂が生じているのも事実です。
そして、ただ単にワンオペ育児に当たる状況が人それぞれという点でもすれ違いが生じます。昼間一人で育児をしている状態がワンオペ育児というママもいれば、夫が単身赴任でほとんどいない状態をワンオペ育児と言うママもいます。反対に夫がいなくても、シングルマザーでもワンオペ育児とは言わないママもいます。
「ワンオペ育児アピールがうざい」「ワンオペという言葉が嫌い」と思うママは、認識の違いが人それぞれなんだということを念頭に置くことで、少しイライラする気持ちが軽減できるかもしれませんね。
イライラを減らす子育て方法が入手できる!ママのためのアプリ、私も入ってるよ!
有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?
子育てって、ホントは最高に幸せ!ワンオペ育児上等!助け合えたらなおよし
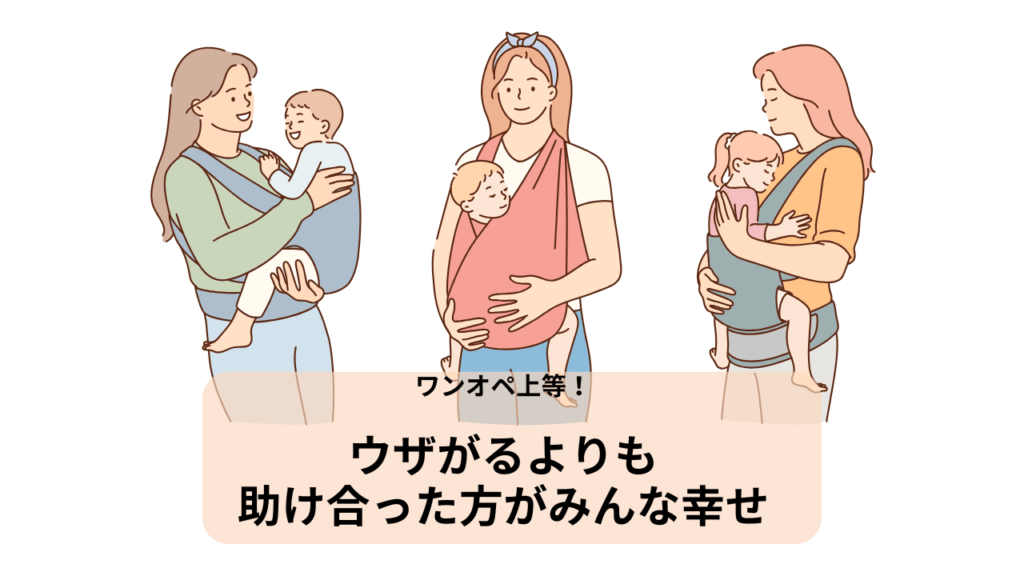
子育てって大変なことがたくさんありますよね!「ママ!ママ!」呼ばれてしんどくなったり、家事が思うように進まなかったり、何をするにも時間がない…。1人で子育てしていると「ワンオペ育児無理…。」となる気持ちも分かります。
でもワンオペ育児って実はとても幸せなことではないですか?子育ての大変なところだけピックアップされていますが、よくよく考えたら楽しいこともいっぱいあります。
専業主婦ママの場合は、パパが仕事をしてくれているおかげでワンオペ育児ができていますし、ワーママの場合は、パパが経験できない子供の成長や可愛い瞬間などをワンオペ中に経験できるという点で幸せなことだと私は思っています。
そして、ネット上でも投稿がありましたが、1人で子育てしている方が楽という意見もあります。
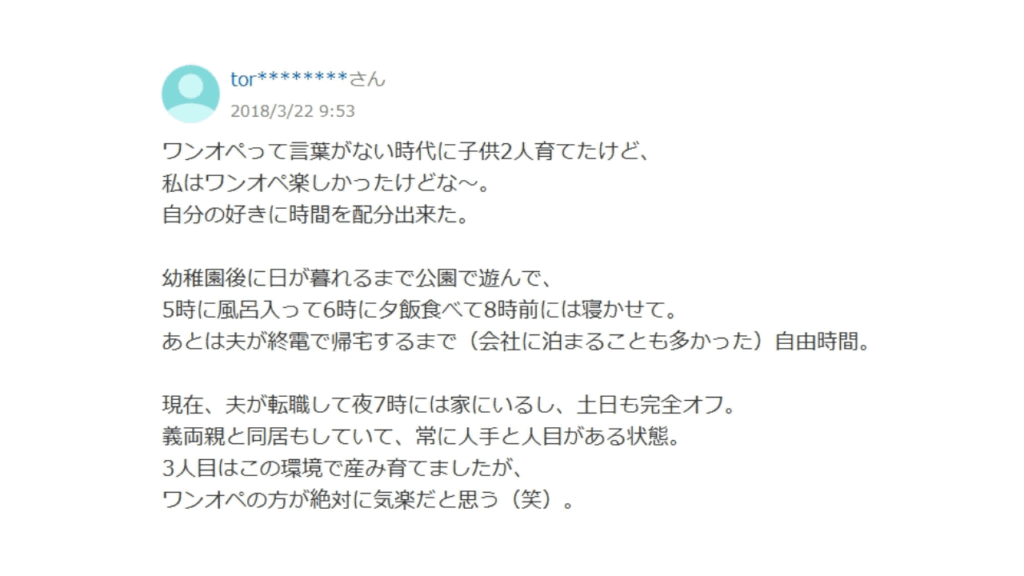
❝ワンオペって言葉がない時代に子供2人育てたけど。私はワンオペ好きだったけどな~。自分の好きに時間を配分出来た。幼稚園後に日が暮れるまで公園で遊んで、5時に風呂入って6時に夕飯食べて8時前には寝かせて。あとは夫が終電で帰宅するまで(会社に泊まることも多かった)自由時間。現在、夫が転職して夜7時には家にいるし、土日も完全オフ。義両親と同居もしていて、常に人手と一目がある状態。3人目はこの環境で産み育てましたが、ワンオペの方が絶対に気楽だと思う(笑)。❞
私は6歳4歳2歳の子育て中ワーママですが、ワンオペ状態で子育てをしている時の方が楽だなと感じる時もあります。夫は家事育児をしてくれますし、休みの日も公園に行ったり家族で外食したり、一緒に過ごす時間が楽しくなるように計画してくれる人です。
しかし平日の保育園のある日は、子供たちを早く寝かせたいので、スムーズにご飯やお風呂などのタスクをこなしたいんです。子供達は、夫がいると遊びたくなったり、お風呂に時間がかかったり、夫が寝る直前に帰ってきたりすると覚醒してしまったりして、私の計画通りに進まないことも多々あります。
そういう時は「1人の方が楽だな~」と感じます。
ただ1人が楽とはいえ、大変なことももちろんあります。そんな時は親族やママ友の助けも借りています。親族は遠方なので、野菜やお米を送ってもらったり、ママ友とはおかずを分け合ったり、買い物に行けない時は買ってきてもらったりしています。
ワンオペ育児に楽しみを見出して、本当に大変な時は頼れる人に頼ったり、サービスを利用したりすると気持ちが楽になりますね。
ワンオペ育児アピールをするママが、どれほど育児に悩んでいるのかは詳しく話を聞かないと分かりませんが、悩みを傾聴して助けてあげられるところは手を貸してあげても良いのではないでしょうか?
「いつもワンオペアピールしててムカつく!」と思うところもあるかもしれませんが、根底は同じ子どもを持つ母親です。お互いに助け合って子育てをしていく方が、お互いにとっても幸せだと私は思っています!
オンラインのママ友ならめっちゃ楽!→ママ友いらないけど寂しい…オンラインのコミュニティーが最強!リアル会もある – 一般社団法人sunnysmile協会
全国にママ友ができる神アプリはここだけ!今すぐ無料インストールしてね♪
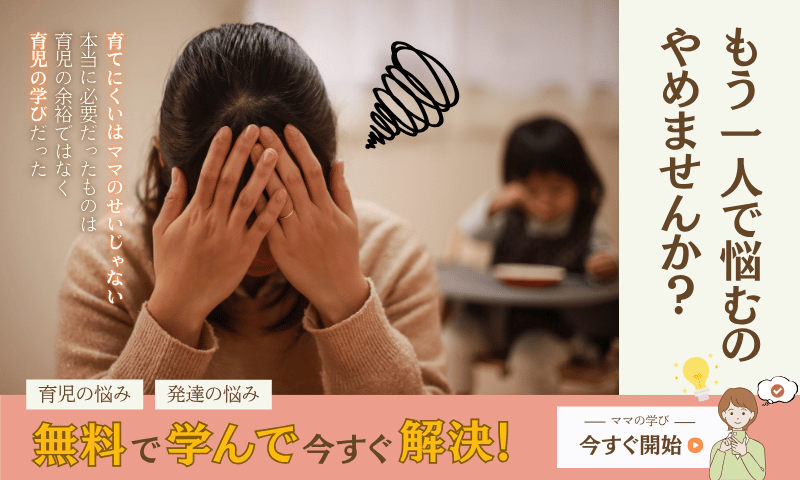
まとめ
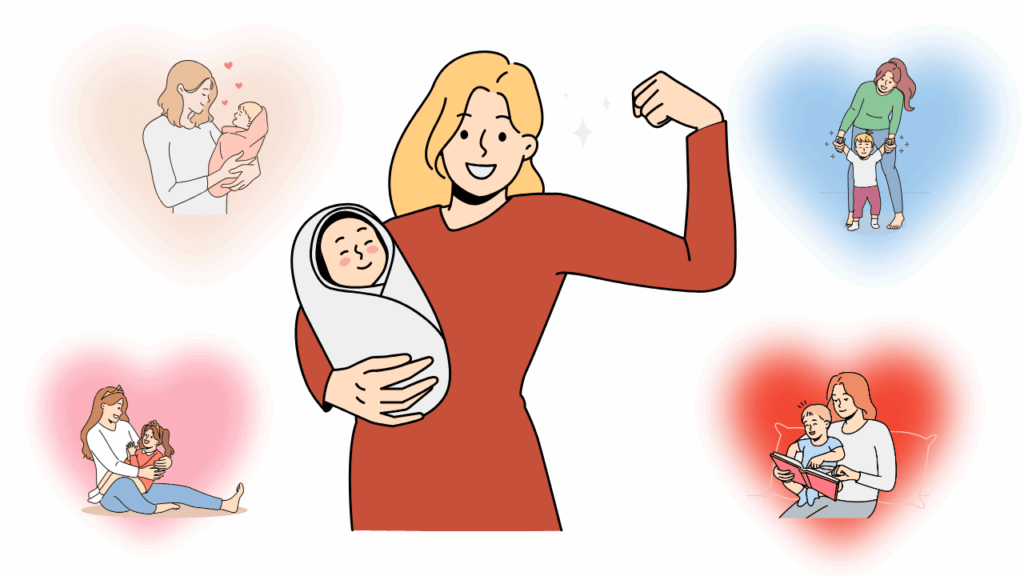
ワンオペ育児アピールをうざいと感じるママのために、この記事では以下のことをまとめました。
- 専業主婦のワンオペ育児アピールうざいという声と、うざいと思わないがなぜアピールするのか疑問に感じる私
- ワンオペ育児の本来の意味と認識の違いによるママ同士の亀裂
- ワンオペ育児って実は幸せ?助け合いながら子育てしていこう!
「ママ同士助け合いながら子育てしていこう!」そういった思考を持つためには、自分のマインドから見直す必要があるかもしれません。私は、以前はワンオペ育児アピールママのように大変なことばかり目について、悲観的になっていたママでした。
それが今では、3人のワンオペ育児も目一杯楽しんで、更にはママ友の手助けまでできるようになりました。自分の子育てを楽しめるようになると余裕が生まれるからです。
私が育休中に子育てを学んだsunnysmile協会では、イライラしない子育て方法や子供の性質に合った声掛けなどを学ぶことができます。1000人以上のマおマがいるので、たくさんの子育て情報を得ることができますし、気軽に相談することもできます。孤独を感じているママにおすすめの場所ですよ♪
1か月間無料で子育て講座を受講できるので、ぜひダウンロードしてね!
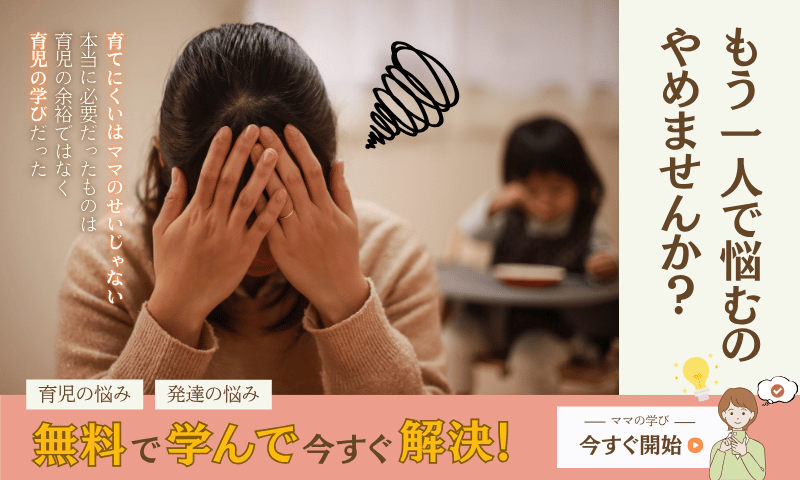
#ワンオペ #育児 #アピール
 一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。
毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

ゆり(4歳、3歳、1歳男の子3人)秋田県出身→東京都
自身の子育てと働き方で悩み、3人目の育休中に子育てコーチングと自分で収入を得る方法を学ぶ。現在は在宅ワークと超ポジティブ育児で悩みなし!
子育て・働き方・健康で悩むママと子供のために活動している。オンライン・オフラインで子育て講座や腸活講座、子育て相談している。
介護福祉士、sunnysmile協会認定子育てコーチングプラチナ講師、ウェルネスステップアドバイザー